新宿駅8番ホームの変死事件 ― 2021年04月05日 09時56分
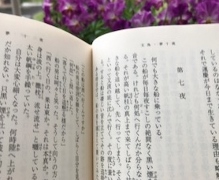
思い出すたびに考え込んでしまうことがある。いやな感じがのこる文章は書きたくないのだが、今日はそのことについて書く。
漱石の短編連作「夢十夜」の中の「第七夜」を読むと、あのときの記憶がよみがえる。漱石はこう書いている。
-自分は益々(ますます)つまらなくなった。とうとう死ぬ事に決心した。それである晩、あたりに人の居ない時分、思い切って海の中へ飛び込んだ。ところが――自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れたその刹那に、急に命が惜しくなった。心の底からよせばよかったと思った。けれども、もう遅い。自分は厭でも応でも海の中へ這入らなければならない。 (略) 自分は何処へ行くんだか判らない船でも、やっぱり乗っている方がよかったと始めて悟りながら、しかもその悟りを利用する事が出来ずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波の方へ静かに落ちて行った。-
週刊誌の記者になって一年ぐらい経ったころだった。事件の新企画が始まり、ぼくはその担当に指名された。見開き2ページのシリーズで、競合する他誌にも同じような看板企画があって、経験の浅いぼくには荷が重かった。
主に殺人を中心にいろんな事件を取材した。人間社会の不条理や人の不運を知って、なぜ、どうして、と戸惑うことばかりだったが、やりきれない気分になったのは自殺の報道である。
なかでも動機のわかりにくい若者の自殺は、ぼくと年齢が近いこともあって、どう原稿を書いてよいのか、悩みに悩んだ。確信の持てない言葉をつないでいると、亡くなった人を冒涜(ぼうとく)しているような気持ちになるのだ。
いまも忘れることのできない事件が発生したのは、1975年の秋だった。場所は、新宿駅の8番ホーム前の線路脇。昼下がりの中央線・八王子行の電車が発車した後、上空から若い男が落ちてきた。即死だった。
8番ホームの目の前は小田急百貨店の外壁が立ちふさがっていて、昼間でも暗い谷底のようである。それにしても、なぜ、大勢の人が集まる、こんなところを死に場所に選んだのだろうか。もし、入線する電車にぶつかったら、大きなニュースになるのはわかっていたはずだ。
詳細は忘れたが、新宿署の調べでは、自死したのは都内に住む地方出身の大学生で、動機は遺書もなく、不明だった。
取材をしても、目立つところもない、おとなしい学生という印象で、実家にも電話したが、自殺の動機についてはまったく思い当たるところはないという。人間関係、失恋、就職の失敗…。取材の甘さは否定できないが、どの仮説も裏付けがとれなかった。
さらにぼくを混乱させたのは、自殺の目撃者の証言だった。
その学生は、小田急百貨店の8階屋上から飛び降りた。落下防止のために張りめぐらされた3、4メートルほどの高さの金属製のネットをよじ登って、柵の外に出て、そこから前方に身を投げたのだ。
ところが、からだが宙に浮かび、背中を向けたまま落ちはじめた途端、彼はくるりとからだを反転させた。同時に、さっと両腕を上げて、屋上の壁のふちに両手をかけた。しかし、アクション映画のシーンならともかく、とても落下しているからだを指先で食い止められるものではない。アッという間に両手はすべるように消えてしまったという。
土壇場になって、死にたくないとおもったのだ。でも、もう引き返しようがない。
そのときの状況と漱石の文章が重なるのである。
この事件の要領を得ない原稿を書きながら、ぼくは何度も、死ななきゃよかったのに、死ななくてもよかったんだろ、とおもった。
どんなことがあっても、生きていればいいのだ、生きていれば。
ぼくは自ら死のうとはおもわないが、自分自身にもこのように言い聞かせるときがある。
漱石の短編連作「夢十夜」の中の「第七夜」を読むと、あのときの記憶がよみがえる。漱石はこう書いている。
-自分は益々(ますます)つまらなくなった。とうとう死ぬ事に決心した。それである晩、あたりに人の居ない時分、思い切って海の中へ飛び込んだ。ところが――自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れたその刹那に、急に命が惜しくなった。心の底からよせばよかったと思った。けれども、もう遅い。自分は厭でも応でも海の中へ這入らなければならない。 (略) 自分は何処へ行くんだか判らない船でも、やっぱり乗っている方がよかったと始めて悟りながら、しかもその悟りを利用する事が出来ずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波の方へ静かに落ちて行った。-
週刊誌の記者になって一年ぐらい経ったころだった。事件の新企画が始まり、ぼくはその担当に指名された。見開き2ページのシリーズで、競合する他誌にも同じような看板企画があって、経験の浅いぼくには荷が重かった。
主に殺人を中心にいろんな事件を取材した。人間社会の不条理や人の不運を知って、なぜ、どうして、と戸惑うことばかりだったが、やりきれない気分になったのは自殺の報道である。
なかでも動機のわかりにくい若者の自殺は、ぼくと年齢が近いこともあって、どう原稿を書いてよいのか、悩みに悩んだ。確信の持てない言葉をつないでいると、亡くなった人を冒涜(ぼうとく)しているような気持ちになるのだ。
いまも忘れることのできない事件が発生したのは、1975年の秋だった。場所は、新宿駅の8番ホーム前の線路脇。昼下がりの中央線・八王子行の電車が発車した後、上空から若い男が落ちてきた。即死だった。
8番ホームの目の前は小田急百貨店の外壁が立ちふさがっていて、昼間でも暗い谷底のようである。それにしても、なぜ、大勢の人が集まる、こんなところを死に場所に選んだのだろうか。もし、入線する電車にぶつかったら、大きなニュースになるのはわかっていたはずだ。
詳細は忘れたが、新宿署の調べでは、自死したのは都内に住む地方出身の大学生で、動機は遺書もなく、不明だった。
取材をしても、目立つところもない、おとなしい学生という印象で、実家にも電話したが、自殺の動機についてはまったく思い当たるところはないという。人間関係、失恋、就職の失敗…。取材の甘さは否定できないが、どの仮説も裏付けがとれなかった。
さらにぼくを混乱させたのは、自殺の目撃者の証言だった。
その学生は、小田急百貨店の8階屋上から飛び降りた。落下防止のために張りめぐらされた3、4メートルほどの高さの金属製のネットをよじ登って、柵の外に出て、そこから前方に身を投げたのだ。
ところが、からだが宙に浮かび、背中を向けたまま落ちはじめた途端、彼はくるりとからだを反転させた。同時に、さっと両腕を上げて、屋上の壁のふちに両手をかけた。しかし、アクション映画のシーンならともかく、とても落下しているからだを指先で食い止められるものではない。アッという間に両手はすべるように消えてしまったという。
土壇場になって、死にたくないとおもったのだ。でも、もう引き返しようがない。
そのときの状況と漱石の文章が重なるのである。
この事件の要領を得ない原稿を書きながら、ぼくは何度も、死ななきゃよかったのに、死ななくてもよかったんだろ、とおもった。
どんなことがあっても、生きていればいいのだ、生きていれば。
ぼくは自ら死のうとはおもわないが、自分自身にもこのように言い聞かせるときがある。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://ichi-yume.asablo.jp/blog/2021/04/05/9364206/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。