本屋の大将・モイッツァンの教え ― 2021年07月10日 12時45分
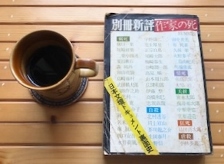
退屈しのぎに、歩いて数分の本屋に行った。ただ並べてある雑誌や本を見るだけで、ああ、いまはこんなことが話題になっているのだなぁとわかるのが、本屋のいいところである。
あのモイッツァンはこんなことを言っていたという。
「本屋はね、並べてある本や雑誌を見るだけで、世の中の動きがわかるんだ」
直接、本人から聞いたわけではない。モイッツァンから本屋の心構えをたたき込まれた人が、ぼくに教えてくれた言葉である。
モイッツァンとは、紀伊国屋書店の名物社長だった故田辺茂一さんのこと。トレードマークの白いヘルメットのような帽子をかぶって、六本木のクラブで楽しそうに話していた姿が目に浮かぶ。
あれは作家の戸川昌子さんが経営するクラブだったろうか。小説担当のデスクは極端な下戸で、水割り一杯でソファをベッド替わりにして高イビキをかいていたが、田舎者のぼくは実物の田辺茂一や戸川昌子が目の前にいるだけで、またひとつ世界がひろがったような気持ちになったものだ。
一見、洒脱な遊び人風のモイッツァンの経営スタイルを伝えてくれた人は、まさにモイッツァン仕込みの本屋さんだった。その人とは紀伊国屋書店が福岡天神コアビルにあったときのO店長である。
彼もまた地元の作家を大切にしていて、ある男性作家が自殺する直前に、その人から届いた手紙を見せてくれた。短い文面には「私は自殺します」と書かれていた。
その遺書は表向きにはならなかったが、作家と街の本屋さんとの間にはこんなにも深い信頼関係があったのである。
ぼくがある本を探しているとき、Oさんがやってきて、その本の名前を尋ねられたことがあった。するとOさんはスタスタと歩き出して、店内の目立たないコーナーの書架までぼくを案内して、いちばん下の棚からその本を抜き取ってくれた。数万冊もの中から迷わずにピンポイントで命中である。まるで店内の情報を手の平に載せているようだった。
「はい。こういうふうにやれるのが本当の本屋なんですよ」
その笑顔がまたよかった。
Oさんは社長のモイッツァンから仕込まれたことを大切に守っていた。
「本屋はほかの店とは違います。お客様はどこからでも入っていいし、どこから出てもいい。お客様もそうおもっているでしょう。言ってみれば、街のなかを歩いているような気分で、店の中に入って来られるんですね。本屋には入り口も出口もない。出るも入るもお客様の自由。そして、並べてある本や雑誌をざっとひとわたり見るだけで、世の中の動きがわかる、それが本屋だ。モイチさんはよくそう言ってましたね」
話は飛ぶが、元NHKのスポーツアナウンサーだった故田辺礼一さんは、モイッツァンの長男である。彼がNHKを辞めるとき、ぼくは彼に会い、その心境をコラムに書いたことがある。父親が築いた本屋の経営に参加すると聞いて、そうか、映像の世界から活字の世界に戻るのかと訳もなくうれしくなったことをおもいだす。
本屋にはいろんな思い出がある。またいつか書こう。
■写真の本は、若いころに数少ない女性の友だちから手渡されたもの。なぜ、『作家の死』(昭和47年8月10日発行、新評社)という表題の本をくれたのか、理由は不明のままである。
あのモイッツァンはこんなことを言っていたという。
「本屋はね、並べてある本や雑誌を見るだけで、世の中の動きがわかるんだ」
直接、本人から聞いたわけではない。モイッツァンから本屋の心構えをたたき込まれた人が、ぼくに教えてくれた言葉である。
モイッツァンとは、紀伊国屋書店の名物社長だった故田辺茂一さんのこと。トレードマークの白いヘルメットのような帽子をかぶって、六本木のクラブで楽しそうに話していた姿が目に浮かぶ。
あれは作家の戸川昌子さんが経営するクラブだったろうか。小説担当のデスクは極端な下戸で、水割り一杯でソファをベッド替わりにして高イビキをかいていたが、田舎者のぼくは実物の田辺茂一や戸川昌子が目の前にいるだけで、またひとつ世界がひろがったような気持ちになったものだ。
一見、洒脱な遊び人風のモイッツァンの経営スタイルを伝えてくれた人は、まさにモイッツァン仕込みの本屋さんだった。その人とは紀伊国屋書店が福岡天神コアビルにあったときのO店長である。
彼もまた地元の作家を大切にしていて、ある男性作家が自殺する直前に、その人から届いた手紙を見せてくれた。短い文面には「私は自殺します」と書かれていた。
その遺書は表向きにはならなかったが、作家と街の本屋さんとの間にはこんなにも深い信頼関係があったのである。
ぼくがある本を探しているとき、Oさんがやってきて、その本の名前を尋ねられたことがあった。するとOさんはスタスタと歩き出して、店内の目立たないコーナーの書架までぼくを案内して、いちばん下の棚からその本を抜き取ってくれた。数万冊もの中から迷わずにピンポイントで命中である。まるで店内の情報を手の平に載せているようだった。
「はい。こういうふうにやれるのが本当の本屋なんですよ」
その笑顔がまたよかった。
Oさんは社長のモイッツァンから仕込まれたことを大切に守っていた。
「本屋はほかの店とは違います。お客様はどこからでも入っていいし、どこから出てもいい。お客様もそうおもっているでしょう。言ってみれば、街のなかを歩いているような気分で、店の中に入って来られるんですね。本屋には入り口も出口もない。出るも入るもお客様の自由。そして、並べてある本や雑誌をざっとひとわたり見るだけで、世の中の動きがわかる、それが本屋だ。モイチさんはよくそう言ってましたね」
話は飛ぶが、元NHKのスポーツアナウンサーだった故田辺礼一さんは、モイッツァンの長男である。彼がNHKを辞めるとき、ぼくは彼に会い、その心境をコラムに書いたことがある。父親が築いた本屋の経営に参加すると聞いて、そうか、映像の世界から活字の世界に戻るのかと訳もなくうれしくなったことをおもいだす。
本屋にはいろんな思い出がある。またいつか書こう。
■写真の本は、若いころに数少ない女性の友だちから手渡されたもの。なぜ、『作家の死』(昭和47年8月10日発行、新評社)という表題の本をくれたのか、理由は不明のままである。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://ichi-yume.asablo.jp/blog/2021/07/10/9396607/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。