国語辞書を買いました ― 2023年05月27日 17時12分
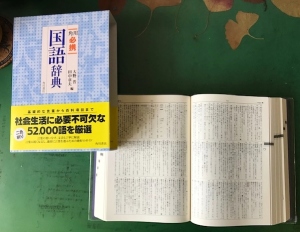
20年ぶりに国語の辞書を買った。角川必携国語辞典(大野晋、田中章夫編)。
井上ひさしが『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室』のなかで、「わたしが気に入っている」と推奨している辞書である。厚さ4センチほどで、持ち運びも苦にならないし、語句の細かなニュアンスがわかりやすく説明されているのがありがたい。
この辞書が手元にあれば、言葉の選び方に自信が持てない場面は格段に少なくなりそうだ。これまで新潮社や集英社の国語辞典にお世話になってきたが、この辞書もすぐになじむだろう。
辞書と言えば、それをつくった編纂人に目が向く。
東京練馬区の石神井町で所帯を持ったとき、アパートから最寄りの石神井公園駅に行く途中の閑静な住宅地にひときわ広い敷地の邸宅があった。庭先には白い漆喰壁の土蔵が建っていた。玄関の表札には「見坊豪紀」の名前が。
あの『明解国語辞典』、『三省堂国語辞典』の生みの親として知られ、「ケンボー先生」と親しまれていた日本語学者である。お顔を見たことはなかったが、そのたたずまいはそこだけ別種の落ち着きがあって、この街全体のステータスを高めていたとおもう。
辞書の話からどんどん離れて行くが、ぼくたち夫婦が暮らしていたアパートの近くには、もうひとりの個性派がいた。見坊氏の邸宅とは比較にならないまでも、それでも立派な一戸建てで、表札は「S・M」。あの中川一郎氏の秘書から自民党代議士、現在は日本維新の会所属の参議院議員になっているお人である。
この人の印象は強烈だった。脱線ついでに、少し思い出話をするとー、
自民党総裁選に立候補した中川氏を追って、N市に出張したとき、その場に居合わせた地元の有力者がぼくに絡んできたことがあった。「記者はいいかげんなことばかり書く」と言うのだ。なぜか、ひとりでカッカカッカして、おまけに「表へ出ろ!」と来た。
もちろん、こちらは相手にしない。「だったら目の前の取材の現場を見てから、記者の仕事を評価しろ。中川さんの前で、見苦しいマネをするな」。そうおもっていた。
中川氏はさすがに大人の風格で、その人物の前で、ぼくのことをちゃんと認めて、取材に応じて、最後にはほめてくれた。(ケンカを売って来たその人物も後に自民党代議士になって、いまも議員バッヂをつけている)
東京に戻って、原稿を出した数日後の夜、突然、中川氏にぴったりついていた秘書のS氏がわがアパートを訪ねてきた。ニコニコ顔をして、大きな紙袋を両手にいっぱい抱えている。品目は忘れたが、とにかく北海道名産の陸と海の美味が玄関口の床に所せましと並べられた。
気配りと行動力の人とは聞いていたが、ここまでとは思わなかった。この人、きっとこのままでは終わらないな、と感じさせるものがあった。
ぼくが東京を去るとき、議員会館に挨拶に行くと、「わかりました。××さんに(就職の口利きを)お願いしましょう」と言い、S氏はすぐさま受話器を取り上げて、九州経済界のドンと言われる人物に電話を入れようとした。とにかく、やることが早いのだ。
実は、そのドンには、すでにぼく師の田原先生から同様の連絡が行っていた。慌てて、紹介の労をお断りした。それがS氏にお会いした最後になった。
いまでも、あのどこか人なつっこい表情で、大きな声を出して、ズケズケ発言している様子をテレビで見るたびに、エネルギッシュだなぁ、変らないなぁ、と感心してしまう。昨今では希少な部類になってしまった、古典的なたたき上げ政治家のひとつのタイプだろう。
こうして記憶をたどりながら書いてみると、なんと書いていないことの多いことか。
井上ひさしは、先に挙げた『作文教室』のなかで、こんなことを言っている。抜粋してつなぐとー、
-私たちの記憶は「短期記憶」と「長期記憶」で成立しているんですね。「長期記憶」というのは、われわれ一人ひとりにとって、たいへん貴重な財産なんです。大事な大事な「長期記憶」。これは字引にもなれば百科事典にもなるわけですね-
ぼくらのなかにあるという長期記憶の百科事典。もしも、これを編纂できたら、いったいどんな辞書になるのだろうか。ぼくはどんな記憶でできている人間なのだろうか。
井上ひさしが『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室』のなかで、「わたしが気に入っている」と推奨している辞書である。厚さ4センチほどで、持ち運びも苦にならないし、語句の細かなニュアンスがわかりやすく説明されているのがありがたい。
この辞書が手元にあれば、言葉の選び方に自信が持てない場面は格段に少なくなりそうだ。これまで新潮社や集英社の国語辞典にお世話になってきたが、この辞書もすぐになじむだろう。
辞書と言えば、それをつくった編纂人に目が向く。
東京練馬区の石神井町で所帯を持ったとき、アパートから最寄りの石神井公園駅に行く途中の閑静な住宅地にひときわ広い敷地の邸宅があった。庭先には白い漆喰壁の土蔵が建っていた。玄関の表札には「見坊豪紀」の名前が。
あの『明解国語辞典』、『三省堂国語辞典』の生みの親として知られ、「ケンボー先生」と親しまれていた日本語学者である。お顔を見たことはなかったが、そのたたずまいはそこだけ別種の落ち着きがあって、この街全体のステータスを高めていたとおもう。
辞書の話からどんどん離れて行くが、ぼくたち夫婦が暮らしていたアパートの近くには、もうひとりの個性派がいた。見坊氏の邸宅とは比較にならないまでも、それでも立派な一戸建てで、表札は「S・M」。あの中川一郎氏の秘書から自民党代議士、現在は日本維新の会所属の参議院議員になっているお人である。
この人の印象は強烈だった。脱線ついでに、少し思い出話をするとー、
自民党総裁選に立候補した中川氏を追って、N市に出張したとき、その場に居合わせた地元の有力者がぼくに絡んできたことがあった。「記者はいいかげんなことばかり書く」と言うのだ。なぜか、ひとりでカッカカッカして、おまけに「表へ出ろ!」と来た。
もちろん、こちらは相手にしない。「だったら目の前の取材の現場を見てから、記者の仕事を評価しろ。中川さんの前で、見苦しいマネをするな」。そうおもっていた。
中川氏はさすがに大人の風格で、その人物の前で、ぼくのことをちゃんと認めて、取材に応じて、最後にはほめてくれた。(ケンカを売って来たその人物も後に自民党代議士になって、いまも議員バッヂをつけている)
東京に戻って、原稿を出した数日後の夜、突然、中川氏にぴったりついていた秘書のS氏がわがアパートを訪ねてきた。ニコニコ顔をして、大きな紙袋を両手にいっぱい抱えている。品目は忘れたが、とにかく北海道名産の陸と海の美味が玄関口の床に所せましと並べられた。
気配りと行動力の人とは聞いていたが、ここまでとは思わなかった。この人、きっとこのままでは終わらないな、と感じさせるものがあった。
ぼくが東京を去るとき、議員会館に挨拶に行くと、「わかりました。××さんに(就職の口利きを)お願いしましょう」と言い、S氏はすぐさま受話器を取り上げて、九州経済界のドンと言われる人物に電話を入れようとした。とにかく、やることが早いのだ。
実は、そのドンには、すでにぼく師の田原先生から同様の連絡が行っていた。慌てて、紹介の労をお断りした。それがS氏にお会いした最後になった。
いまでも、あのどこか人なつっこい表情で、大きな声を出して、ズケズケ発言している様子をテレビで見るたびに、エネルギッシュだなぁ、変らないなぁ、と感心してしまう。昨今では希少な部類になってしまった、古典的なたたき上げ政治家のひとつのタイプだろう。
こうして記憶をたどりながら書いてみると、なんと書いていないことの多いことか。
井上ひさしは、先に挙げた『作文教室』のなかで、こんなことを言っている。抜粋してつなぐとー、
-私たちの記憶は「短期記憶」と「長期記憶」で成立しているんですね。「長期記憶」というのは、われわれ一人ひとりにとって、たいへん貴重な財産なんです。大事な大事な「長期記憶」。これは字引にもなれば百科事典にもなるわけですね-
ぼくらのなかにあるという長期記憶の百科事典。もしも、これを編纂できたら、いったいどんな辞書になるのだろうか。ぼくはどんな記憶でできている人間なのだろうか。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://ichi-yume.asablo.jp/blog/2023/05/27/9589586/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。