観察するオモシロサ ― 2021年04月03日 11時48分

道ばたのあちこちに野草のスミレの花が咲いている。こぼれダネが散らばったのだろう、スミレたちの小さな花畑ができていた。濃い紫色もあれば、うすいのもある。花の形も同じように見えて、みな違う。こうやって寄り添うにして咲くのも、人間と変わらないな。
目に映るモノを写真で切り取っていると、観察という行為のおもしろさに気づかされる。
ずいぶん前の話だが、ある制作会社から福岡・天神の冊子をつくりたい、ついては何かユニークな切り口はないかという相談があった。
そんな注文なら、おやすい御用である。さっそく、カメラをぶら下げて(そのときはまだスマホがかったので)、「天神の動物」を仮のテーマにして、街に出た。
こういうときに、テーマを絞って観察するかどうかで、結果は大きく変わってくる。「××を探す」というアンテナを立てていると、向こうの方から情報は飛び込んでくるものだ。
地面を観るとマンホールの蓋に、ビルに目をやると企業のロゴマークに、視線を上げると街灯に、いろんな動物がいた。そこで、ぼくは「天神は動物園」という企画を提案して、冊子の特集ページをかざったことがある。
ちょっと専門的なことを言うと、あるテーマの「のぼり旗」を立てる。その「のぼり旗」に関連する情報を集める。すると、そのテーマの特集や本ができる。これが「編集」の考え方の基本である。
たとえば100人の人がいて、これを整理しろと言われたときにも、編集のノウハウが役に立つ。「背の低い順に」、「50音順に」、「出身地別に」、「兄弟の人数別に」、「既婚者と未婚者別に」など、いくらでも整理する方法はある。そして、この編集の技術と観察を組み合わせるとマーケティングのコツもわかってくる。
ある狭いエリアの住民たちの暮らしぶりを調べたいのなら、最寄りのスーパーに入るのもひとつの有効な手段になる。
そこでの「のぼり旗」は高級食材。「観察」するのは、肉売り場の牛肉である。和牛の高額品の品ぞろえはどうか。それをチェックするだけでも、周辺の人々の食費にかける支出について、ある程度の判断がつく。
停まっている車も観察の対象になる。ここでの「のぼり旗」は高級車。軽の汚れた中古車ばかりが停まっているスーパーには、まず高級な牛肉は並んでいないものだ。
エリア調査の専門家によれば、車でざっとまわりを走って、窓辺に干してある洗濯物を見るだけで、その地域の人々の世帯構造や所得のおおよその見当がつくという。いわゆる「土手観(ドテカン)」というやつだ。ある大手外食企業の出店計画の担当者は、地名を聞くだけで、瞬時に売上を予測していた。
かたい話はこの辺にして、私見だが、観察力の鋭さでは、女性の方が男性よりもはるかに上手だとおもう。
女性社員たちが職場の男たちの身に着けている背広やネクタイ、靴、さらには髪形からクセ、人柄まで観察して、男性の魅力度をああだ、こうだと評定する。ああやって、日々、観察力を鍛えあげているのだ。そんな彼女たちにいったん嫌われたら、もうオシマイである。
ところが、ぼくもそうだが、男どもはそういう女性たちの眼力に気づいていない。そんなことよりも、ぼくらの世代は「男は中身で勝負」なんて言いだしかねない。
スミレの花の話から思わぬ方向に脱線したが、観察とマーケティングのノウハウには共通するところが多い。だから、これからますます女性たちの活躍の場は広がっていくとおもう。
ぶらりと散歩にでるとき、ひところはやった「路上観察学会」のように、ちょっと立ち止まって、スマホで写真を撮るのは、案外、ボケ防止になるかもしれない。
目に映るモノを写真で切り取っていると、観察という行為のおもしろさに気づかされる。
ずいぶん前の話だが、ある制作会社から福岡・天神の冊子をつくりたい、ついては何かユニークな切り口はないかという相談があった。
そんな注文なら、おやすい御用である。さっそく、カメラをぶら下げて(そのときはまだスマホがかったので)、「天神の動物」を仮のテーマにして、街に出た。
こういうときに、テーマを絞って観察するかどうかで、結果は大きく変わってくる。「××を探す」というアンテナを立てていると、向こうの方から情報は飛び込んでくるものだ。
地面を観るとマンホールの蓋に、ビルに目をやると企業のロゴマークに、視線を上げると街灯に、いろんな動物がいた。そこで、ぼくは「天神は動物園」という企画を提案して、冊子の特集ページをかざったことがある。
ちょっと専門的なことを言うと、あるテーマの「のぼり旗」を立てる。その「のぼり旗」に関連する情報を集める。すると、そのテーマの特集や本ができる。これが「編集」の考え方の基本である。
たとえば100人の人がいて、これを整理しろと言われたときにも、編集のノウハウが役に立つ。「背の低い順に」、「50音順に」、「出身地別に」、「兄弟の人数別に」、「既婚者と未婚者別に」など、いくらでも整理する方法はある。そして、この編集の技術と観察を組み合わせるとマーケティングのコツもわかってくる。
ある狭いエリアの住民たちの暮らしぶりを調べたいのなら、最寄りのスーパーに入るのもひとつの有効な手段になる。
そこでの「のぼり旗」は高級食材。「観察」するのは、肉売り場の牛肉である。和牛の高額品の品ぞろえはどうか。それをチェックするだけでも、周辺の人々の食費にかける支出について、ある程度の判断がつく。
停まっている車も観察の対象になる。ここでの「のぼり旗」は高級車。軽の汚れた中古車ばかりが停まっているスーパーには、まず高級な牛肉は並んでいないものだ。
エリア調査の専門家によれば、車でざっとまわりを走って、窓辺に干してある洗濯物を見るだけで、その地域の人々の世帯構造や所得のおおよその見当がつくという。いわゆる「土手観(ドテカン)」というやつだ。ある大手外食企業の出店計画の担当者は、地名を聞くだけで、瞬時に売上を予測していた。
かたい話はこの辺にして、私見だが、観察力の鋭さでは、女性の方が男性よりもはるかに上手だとおもう。
女性社員たちが職場の男たちの身に着けている背広やネクタイ、靴、さらには髪形からクセ、人柄まで観察して、男性の魅力度をああだ、こうだと評定する。ああやって、日々、観察力を鍛えあげているのだ。そんな彼女たちにいったん嫌われたら、もうオシマイである。
ところが、ぼくもそうだが、男どもはそういう女性たちの眼力に気づいていない。そんなことよりも、ぼくらの世代は「男は中身で勝負」なんて言いだしかねない。
スミレの花の話から思わぬ方向に脱線したが、観察とマーケティングのノウハウには共通するところが多い。だから、これからますます女性たちの活躍の場は広がっていくとおもう。
ぶらりと散歩にでるとき、ひところはやった「路上観察学会」のように、ちょっと立ち止まって、スマホで写真を撮るのは、案外、ボケ防止になるかもしれない。
新宿駅8番ホームの変死事件 ― 2021年04月05日 09時56分
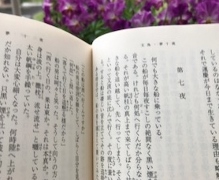
思い出すたびに考え込んでしまうことがある。いやな感じがのこる文章は書きたくないのだが、今日はそのことについて書く。
漱石の短編連作「夢十夜」の中の「第七夜」を読むと、あのときの記憶がよみがえる。漱石はこう書いている。
-自分は益々(ますます)つまらなくなった。とうとう死ぬ事に決心した。それである晩、あたりに人の居ない時分、思い切って海の中へ飛び込んだ。ところが――自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れたその刹那に、急に命が惜しくなった。心の底からよせばよかったと思った。けれども、もう遅い。自分は厭でも応でも海の中へ這入らなければならない。 (略) 自分は何処へ行くんだか判らない船でも、やっぱり乗っている方がよかったと始めて悟りながら、しかもその悟りを利用する事が出来ずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波の方へ静かに落ちて行った。-
週刊誌の記者になって一年ぐらい経ったころだった。事件の新企画が始まり、ぼくはその担当に指名された。見開き2ページのシリーズで、競合する他誌にも同じような看板企画があって、経験の浅いぼくには荷が重かった。
主に殺人を中心にいろんな事件を取材した。人間社会の不条理や人の不運を知って、なぜ、どうして、と戸惑うことばかりだったが、やりきれない気分になったのは自殺の報道である。
なかでも動機のわかりにくい若者の自殺は、ぼくと年齢が近いこともあって、どう原稿を書いてよいのか、悩みに悩んだ。確信の持てない言葉をつないでいると、亡くなった人を冒涜(ぼうとく)しているような気持ちになるのだ。
いまも忘れることのできない事件が発生したのは、1975年の秋だった。場所は、新宿駅の8番ホーム前の線路脇。昼下がりの中央線・八王子行の電車が発車した後、上空から若い男が落ちてきた。即死だった。
8番ホームの目の前は小田急百貨店の外壁が立ちふさがっていて、昼間でも暗い谷底のようである。それにしても、なぜ、大勢の人が集まる、こんなところを死に場所に選んだのだろうか。もし、入線する電車にぶつかったら、大きなニュースになるのはわかっていたはずだ。
詳細は忘れたが、新宿署の調べでは、自死したのは都内に住む地方出身の大学生で、動機は遺書もなく、不明だった。
取材をしても、目立つところもない、おとなしい学生という印象で、実家にも電話したが、自殺の動機についてはまったく思い当たるところはないという。人間関係、失恋、就職の失敗…。取材の甘さは否定できないが、どの仮説も裏付けがとれなかった。
さらにぼくを混乱させたのは、自殺の目撃者の証言だった。
その学生は、小田急百貨店の8階屋上から飛び降りた。落下防止のために張りめぐらされた3、4メートルほどの高さの金属製のネットをよじ登って、柵の外に出て、そこから前方に身を投げたのだ。
ところが、からだが宙に浮かび、背中を向けたまま落ちはじめた途端、彼はくるりとからだを反転させた。同時に、さっと両腕を上げて、屋上の壁のふちに両手をかけた。しかし、アクション映画のシーンならともかく、とても落下しているからだを指先で食い止められるものではない。アッという間に両手はすべるように消えてしまったという。
土壇場になって、死にたくないとおもったのだ。でも、もう引き返しようがない。
そのときの状況と漱石の文章が重なるのである。
この事件の要領を得ない原稿を書きながら、ぼくは何度も、死ななきゃよかったのに、死ななくてもよかったんだろ、とおもった。
どんなことがあっても、生きていればいいのだ、生きていれば。
ぼくは自ら死のうとはおもわないが、自分自身にもこのように言い聞かせるときがある。
漱石の短編連作「夢十夜」の中の「第七夜」を読むと、あのときの記憶がよみがえる。漱石はこう書いている。
-自分は益々(ますます)つまらなくなった。とうとう死ぬ事に決心した。それである晩、あたりに人の居ない時分、思い切って海の中へ飛び込んだ。ところが――自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れたその刹那に、急に命が惜しくなった。心の底からよせばよかったと思った。けれども、もう遅い。自分は厭でも応でも海の中へ這入らなければならない。 (略) 自分は何処へ行くんだか判らない船でも、やっぱり乗っている方がよかったと始めて悟りながら、しかもその悟りを利用する事が出来ずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波の方へ静かに落ちて行った。-
週刊誌の記者になって一年ぐらい経ったころだった。事件の新企画が始まり、ぼくはその担当に指名された。見開き2ページのシリーズで、競合する他誌にも同じような看板企画があって、経験の浅いぼくには荷が重かった。
主に殺人を中心にいろんな事件を取材した。人間社会の不条理や人の不運を知って、なぜ、どうして、と戸惑うことばかりだったが、やりきれない気分になったのは自殺の報道である。
なかでも動機のわかりにくい若者の自殺は、ぼくと年齢が近いこともあって、どう原稿を書いてよいのか、悩みに悩んだ。確信の持てない言葉をつないでいると、亡くなった人を冒涜(ぼうとく)しているような気持ちになるのだ。
いまも忘れることのできない事件が発生したのは、1975年の秋だった。場所は、新宿駅の8番ホーム前の線路脇。昼下がりの中央線・八王子行の電車が発車した後、上空から若い男が落ちてきた。即死だった。
8番ホームの目の前は小田急百貨店の外壁が立ちふさがっていて、昼間でも暗い谷底のようである。それにしても、なぜ、大勢の人が集まる、こんなところを死に場所に選んだのだろうか。もし、入線する電車にぶつかったら、大きなニュースになるのはわかっていたはずだ。
詳細は忘れたが、新宿署の調べでは、自死したのは都内に住む地方出身の大学生で、動機は遺書もなく、不明だった。
取材をしても、目立つところもない、おとなしい学生という印象で、実家にも電話したが、自殺の動機についてはまったく思い当たるところはないという。人間関係、失恋、就職の失敗…。取材の甘さは否定できないが、どの仮説も裏付けがとれなかった。
さらにぼくを混乱させたのは、自殺の目撃者の証言だった。
その学生は、小田急百貨店の8階屋上から飛び降りた。落下防止のために張りめぐらされた3、4メートルほどの高さの金属製のネットをよじ登って、柵の外に出て、そこから前方に身を投げたのだ。
ところが、からだが宙に浮かび、背中を向けたまま落ちはじめた途端、彼はくるりとからだを反転させた。同時に、さっと両腕を上げて、屋上の壁のふちに両手をかけた。しかし、アクション映画のシーンならともかく、とても落下しているからだを指先で食い止められるものではない。アッという間に両手はすべるように消えてしまったという。
土壇場になって、死にたくないとおもったのだ。でも、もう引き返しようがない。
そのときの状況と漱石の文章が重なるのである。
この事件の要領を得ない原稿を書きながら、ぼくは何度も、死ななきゃよかったのに、死ななくてもよかったんだろ、とおもった。
どんなことがあっても、生きていればいいのだ、生きていれば。
ぼくは自ら死のうとはおもわないが、自分自身にもこのように言い聞かせるときがある。
おふくろの味、伝わるか ― 2021年04月06日 17時43分

今日も、朝から夕食のことを考えていた。もう5、6年も主夫をやっているのに、いまだにいちばん悩むのは食事の献立である。いちおう栄養のバランスを考える。それから旬の食材をあれこれおもい浮かべる。
タケノコはまだ高いよな。スナップエンドウやブロッコリーはそろそろ終わりか。大羽イワシとさくら鯛は、この間、食べたし、いまはアサリか。でも、砂ぬきがなぁ。そうだ、イサキが出はじめたか。まてまて、冷蔵庫にアジの開きがあったっけ。
値段、料理にかかる手間、そして、おいしいと言ってくれるかどうか。メニューが決まるまではどうも落ち着かない。
迷った末に、今夜のメニューは「豚のコマ肉を使ったカレー味の肉だんご焼き」に決定。安くて、簡単、家族みんな好きだから、困ったときの切り札のひとつだ。
この料理用に買ったのは豚のコマ肉2パック(約500g)だけ。ほかに必要なニラ、卵、カレー粉、片栗粉、塩はある。いっぱいつくって、明日のカミさんの弁当にも入れてもらおう。
調理方法はすごく簡単だ。まず豚のコマ肉をドーンとまな板にのせて、包丁の先で肉片を広げながら、スッ、スッと2センチほどの幅に切り分ける。こいつをステンレスのボールにドサッと入れる。次に、ニラの束を刻んで、これもボールに放り込む。
そこに塩をパラパラパラとふって、とき卵をドバッと加えて、カレー粉をバッ、バッ、バッ、片栗粉をパッ、パッ、パッと入れる。
いちいち計量器は使わない、みんな見当で量を調整する。もっとスパイシーにしたければ、クミンやガムマサラ、コリアンダーをふりかけてもいい。あとは全体がなじむように手でこねて、食べやすい大きさにまるめるだけ。
切って、入れて、混ぜて、形にするだけだ。技術なんて要らない。味みもしない。ただし、ニラとカレー粉は惜しまない方がいい。肉だんごはきつく固めるよりも、かるく形をととのえる程度の方が食感はよい。
あとはフライパンにやや多めのサラダオイルを熱して、ほどよく焼きめをつけて、蒸し焼きにして、中まで火が通ったら完成である。味が物足りないときは、食べるときにウスターソースをつければOKだ。
先ほどだんごの段階までつくり終わったので、いまこのブログを書いている。
もともとは母の手料理だった。母は、豚肉はコマではなく、バラ肉や肩ロースの薄切りを、ニンニクの葉があれば、ニラよりもそちらの方を使っていた。また手でまるめずに、水溶き片栗粉の中に、卵やカレー粉、塩を混ぜた上で、肉ほかを入れてから、箸をつかって肉片とニンニクの葉をかるくまとめて、ちゃんと油で揚げていた。
その方がやわらかく仕上がって、肉汁も多くて、食感もよく、ずっとおいしい。けれども、ぼくは油の処理が面倒なので、全部を一緒くたにして、ただ焼くだけという楽なやり方を編み出した。
母はそうやって、一つひとつ手を抜かずに、毎日つくってくれて、大事に育ててくれたのだ。注いでくれた愛情がどんなにこまやかだったか、自分が親になるまで気がつかなかった。
そんなことを思い出しながら、ぼくは家族に「どうだ、うまいだろう」と半ば強引に同意を求めるのである。
■写真は、だんごにしたところ。ふたつの皿いっぱいになった。
タケノコはまだ高いよな。スナップエンドウやブロッコリーはそろそろ終わりか。大羽イワシとさくら鯛は、この間、食べたし、いまはアサリか。でも、砂ぬきがなぁ。そうだ、イサキが出はじめたか。まてまて、冷蔵庫にアジの開きがあったっけ。
値段、料理にかかる手間、そして、おいしいと言ってくれるかどうか。メニューが決まるまではどうも落ち着かない。
迷った末に、今夜のメニューは「豚のコマ肉を使ったカレー味の肉だんご焼き」に決定。安くて、簡単、家族みんな好きだから、困ったときの切り札のひとつだ。
この料理用に買ったのは豚のコマ肉2パック(約500g)だけ。ほかに必要なニラ、卵、カレー粉、片栗粉、塩はある。いっぱいつくって、明日のカミさんの弁当にも入れてもらおう。
調理方法はすごく簡単だ。まず豚のコマ肉をドーンとまな板にのせて、包丁の先で肉片を広げながら、スッ、スッと2センチほどの幅に切り分ける。こいつをステンレスのボールにドサッと入れる。次に、ニラの束を刻んで、これもボールに放り込む。
そこに塩をパラパラパラとふって、とき卵をドバッと加えて、カレー粉をバッ、バッ、バッ、片栗粉をパッ、パッ、パッと入れる。
いちいち計量器は使わない、みんな見当で量を調整する。もっとスパイシーにしたければ、クミンやガムマサラ、コリアンダーをふりかけてもいい。あとは全体がなじむように手でこねて、食べやすい大きさにまるめるだけ。
切って、入れて、混ぜて、形にするだけだ。技術なんて要らない。味みもしない。ただし、ニラとカレー粉は惜しまない方がいい。肉だんごはきつく固めるよりも、かるく形をととのえる程度の方が食感はよい。
あとはフライパンにやや多めのサラダオイルを熱して、ほどよく焼きめをつけて、蒸し焼きにして、中まで火が通ったら完成である。味が物足りないときは、食べるときにウスターソースをつければOKだ。
先ほどだんごの段階までつくり終わったので、いまこのブログを書いている。
もともとは母の手料理だった。母は、豚肉はコマではなく、バラ肉や肩ロースの薄切りを、ニンニクの葉があれば、ニラよりもそちらの方を使っていた。また手でまるめずに、水溶き片栗粉の中に、卵やカレー粉、塩を混ぜた上で、肉ほかを入れてから、箸をつかって肉片とニンニクの葉をかるくまとめて、ちゃんと油で揚げていた。
その方がやわらかく仕上がって、肉汁も多くて、食感もよく、ずっとおいしい。けれども、ぼくは油の処理が面倒なので、全部を一緒くたにして、ただ焼くだけという楽なやり方を編み出した。
母はそうやって、一つひとつ手を抜かずに、毎日つくってくれて、大事に育ててくれたのだ。注いでくれた愛情がどんなにこまやかだったか、自分が親になるまで気がつかなかった。
そんなことを思い出しながら、ぼくは家族に「どうだ、うまいだろう」と半ば強引に同意を求めるのである。
■写真は、だんごにしたところ。ふたつの皿いっぱいになった。
レンゲ畑は語りかける ― 2021年04月09日 15時13分

運動不足解消を兼ねて、リュックを背負い、歩いて買い物に出かけた。住宅が立ち並んでいる途中のすき間に、そこだけピンク色に染まったレンゲ畑がある。
鹿児島の田舎町、そして小倉の郊外に住んでいたころは、春になるとまわりの田んぼはレンゲの花で埋めつくされた。そこは赤やピンクの海原のようだった。
モンシロチョウがくっついたり、はなれたりしながら、ひらひら飛んでいるなかを走って、レンゲの花畑に寝ころんで、青い空を見上げると、雲雀(ひばり)のにぎやかなさえずりが落ちてきた。耳元ではミツバチのブーンいう羽音が聞こえる。忙しそうに蜜を吸い、両脚には黄色い花粉の小さな玉をつけている。女の子たちはレンゲの花を摘んで、首飾りをいくつもつくっていた。
そんな日本の春の光景は、ほとんどなくなってしまった。あんなに広いレンゲ畑はどこにもない。雲雀の鳴き声も聞こえない。かわいいニホンミツバチもいなくなった。
あって当たり前だった自然との営みを、ぼくたちの世代は猛烈な速さで根絶やしにしようとしている。たった五、六十年前にはふつうだったように子どもたちを遊ばせたくても、都会ではどうすることもできない。
この一反ほどの畑を所有している農家の人は、ぼくの知り合いでも何でもないが、見たところは80歳ぐらいだろうか。毎年、畑が終わったら田んぼにして、五月には若葉色の稲穂をとりまく畔(あぜ)に、赤紫や青紫、純白の花しょうぶをいっぱい咲かせてくれる。
近くにいる友人の話では、かつては田植えの後に、アイガモをはなしていたという。レンゲは空気中の窒素を取り込んで養分にする。アイガモを利用するのは自然農法のひとつ。福岡市内の住宅やアパートが立て込んだところにも、まだ、こんな立派なお百姓さんがいる。
レンゲの花を撮影しながら、ぼくはNHKで放送された半藤一利さんの追悼番組をおもいだして、もういちど録画を見た。そのなかで半藤さんは、司馬遼太郎さんが亡くなる一年前に、ホテルのバーで語り合った内容にふれている。
司馬さんはこんなことを言っていたという。
-わたしたちは、平等で差別のない、みんなが同じ大地に立って生きるという戦後の民主主義がいちばん正しいと信じて、ていねいに国家をつくろうとしてきた。でも、その努力はあまり強くなかったのかな。土地問題だってそうだ。先祖代々、大切にしてきた土地を、みんなでカネ儲けの対象にしてしまった。こんな馬鹿なことがあるか。
でも、最後の努力で、やろうじゃないか。まだ国民の70%が同意できるようなことがあるんじゃないか。それは、これ以上、自然を壊さないことだ。孫やひ孫たちに美しい川を残して、ハゲ山ばかりなんてことじゃなくて、魚釣りができる川を、トンボとりができる野原をそのまま残すような形で、自然をこわさないようにする。これなら国民の70%は同意するとおもう。できないことはない、まだ間に合うとおもう。-
半藤さんは「明治の日本も、戦後の日本も、解決しておかなければいけないことを、みんな後まわしにしてしまった」と発言していた。
司馬さんは4半世紀も前の1996年に、半藤さんはことし1月に亡くなった。日本人がつくってきた歴史を鋭く考察して、いまやらなければいけない本質の課題を指し示してくれる賢人も相次いでいなくなった。
だが、わが街の片隅には自然と共存する大切さをわかっている人もいる。畑をまもり、タネを撒き続ける人がいるから、こうして毎年、レンゲの花はきれいに咲くのである。
鹿児島の田舎町、そして小倉の郊外に住んでいたころは、春になるとまわりの田んぼはレンゲの花で埋めつくされた。そこは赤やピンクの海原のようだった。
モンシロチョウがくっついたり、はなれたりしながら、ひらひら飛んでいるなかを走って、レンゲの花畑に寝ころんで、青い空を見上げると、雲雀(ひばり)のにぎやかなさえずりが落ちてきた。耳元ではミツバチのブーンいう羽音が聞こえる。忙しそうに蜜を吸い、両脚には黄色い花粉の小さな玉をつけている。女の子たちはレンゲの花を摘んで、首飾りをいくつもつくっていた。
そんな日本の春の光景は、ほとんどなくなってしまった。あんなに広いレンゲ畑はどこにもない。雲雀の鳴き声も聞こえない。かわいいニホンミツバチもいなくなった。
あって当たり前だった自然との営みを、ぼくたちの世代は猛烈な速さで根絶やしにしようとしている。たった五、六十年前にはふつうだったように子どもたちを遊ばせたくても、都会ではどうすることもできない。
この一反ほどの畑を所有している農家の人は、ぼくの知り合いでも何でもないが、見たところは80歳ぐらいだろうか。毎年、畑が終わったら田んぼにして、五月には若葉色の稲穂をとりまく畔(あぜ)に、赤紫や青紫、純白の花しょうぶをいっぱい咲かせてくれる。
近くにいる友人の話では、かつては田植えの後に、アイガモをはなしていたという。レンゲは空気中の窒素を取り込んで養分にする。アイガモを利用するのは自然農法のひとつ。福岡市内の住宅やアパートが立て込んだところにも、まだ、こんな立派なお百姓さんがいる。
レンゲの花を撮影しながら、ぼくはNHKで放送された半藤一利さんの追悼番組をおもいだして、もういちど録画を見た。そのなかで半藤さんは、司馬遼太郎さんが亡くなる一年前に、ホテルのバーで語り合った内容にふれている。
司馬さんはこんなことを言っていたという。
-わたしたちは、平等で差別のない、みんなが同じ大地に立って生きるという戦後の民主主義がいちばん正しいと信じて、ていねいに国家をつくろうとしてきた。でも、その努力はあまり強くなかったのかな。土地問題だってそうだ。先祖代々、大切にしてきた土地を、みんなでカネ儲けの対象にしてしまった。こんな馬鹿なことがあるか。
でも、最後の努力で、やろうじゃないか。まだ国民の70%が同意できるようなことがあるんじゃないか。それは、これ以上、自然を壊さないことだ。孫やひ孫たちに美しい川を残して、ハゲ山ばかりなんてことじゃなくて、魚釣りができる川を、トンボとりができる野原をそのまま残すような形で、自然をこわさないようにする。これなら国民の70%は同意するとおもう。できないことはない、まだ間に合うとおもう。-
半藤さんは「明治の日本も、戦後の日本も、解決しておかなければいけないことを、みんな後まわしにしてしまった」と発言していた。
司馬さんは4半世紀も前の1996年に、半藤さんはことし1月に亡くなった。日本人がつくってきた歴史を鋭く考察して、いまやらなければいけない本質の課題を指し示してくれる賢人も相次いでいなくなった。
だが、わが街の片隅には自然と共存する大切さをわかっている人もいる。畑をまもり、タネを撒き続ける人がいるから、こうして毎年、レンゲの花はきれいに咲くのである。
「古書の森日記」に想う ― 2021年04月17日 23時07分

夜来からの雨が上がった午前中、新緑に彩られた室見川をわたって、足の向くままブックオフに行った。
いつものように100円の文庫本コーナーの背表紙を、ア行の作者の名前からワ行までたどるように見ていく。
いま売れているらしい作家たちの本の多いこと。それも新刊ピカピカがズラリ。こんなにどんどん出版して、売れない在庫の山を次々に古本業界にまわして、出版界は大丈夫だろうか。
本もまたモノとして、すっかり消耗品になったらしい。ということは、作家も消耗品になったのだろうか。その勢いはますます加速しているような気がしてならない。
取り立てて、買いたい本はない。人だかりしているマンガコーナーを横目に、さっさと店を出た。
学生時代に親しんだ古本屋には、歴史を重ねた古本屋ならではの落ち着いた味わいがあった。大学に通う大通りの左右には、小は間口2間ほどから、大は4、5間ほどの古本屋が並んでいて、ガラス窓の奥の飾り棚には「××全集」、「××選集」の分厚い本の束がいくつも積まれていた。
カネが入ったら、あの全集を買ってやるぞ。そうおもいながらも、ついに実現しなかった。それらの全集の束を見つめていた学生はぼくだけではなかった。
古本屋で手にした本の巻末のページには、見ず知らずの先輩諸兄のサインや読後の一文が書き込まれていたり、蔵書版が押されている本もあった。
こうして一冊の本がぼくの手に来るまでの道のりを想像するだけでも、知的な興奮を覚えたものだ。田舎者のぼくにとって、学生街の古本屋は「これから知る教養」との出会いの場だった。
ずっと読み継がれている本は、自分も読まなければとおもい、専門書の棚の前ではその測り知れない学問の奥の深さに圧倒され、いま話題の新刊書を見つけると、シメタとおもった。
古本と言えば、亡くなった友人のノンフィクション作家・黒岩比佐子さんのことを想い出す。彼女のブログ『古書の森日記 by Hisaco』には多くのファンがついていた。
ひところ福岡市内で暮らしていて、一緒に仕事をしたこともある。狭い自宅にも来てくれた。出身地の東京に戻ってからは、福岡に来るたびに、ぼくの事務所に立ち寄って、帰りの飛行機の時刻いっぱいまで、彼女が書いている原稿の話で盛り上がった。贈ってくれた本はいまも手元においている。
彼女のことはとても軽々しく書けない。
最後の作品になった『パンとペン 社会主義者・堺利彦と「売文社」の闘い』の発行は2010年10月7日。彼女がすい臓ガンで亡くなったのは翌11月17日。その後で、読売文学賞「評論・伝記賞」が受与された。
福岡にいたころに着想を得た処女作『音のない記憶 ろうあの天才 写真家井之上孝治の生涯』も、『「食道楽」の人 村井弦斎』(サントリー学芸賞)も、無名の彼女が自分の意思で書きあげた原稿を持って、出版社を飛び込みでまわって、それぞれ文芸春秋と岩波書店の編集者から認められて出版された。
いま、そんな書き手がどれほどいるだろうか。
五木寛之氏からの信頼も厚く、彼の『百寺巡礼』の詳細な資料を集めて、書きやすく整理したのも黒岩さんである。慶應義塾では女子ソフトテニス部のキャプテンをして、そちらの方でも大活躍された。
「キャプテンだから、がんばらないと。ランニングでも、どんなにきつくても、絶対に先頭を走っていました」と言っていた。
飾らず、威張らず、地道に、コツコツと励み、体力の限界まで、ベストを尽くす人だった。一日中、国会図書館もこもって、吐きそうになるのを我慢して、古い新聞のマイクロフィルムを読み漁っていたと聞いたこともある。取材で海外にも足を伸ばしていた。あれほど徹底的に調べあげる人に会ったことがない。
黒岩さんが亡くなったのは52歳。
「子どものころから、いつか自分の本を書きたいというのが夢でした。わたしが死んでも、一冊でもいいから、ずっと後まで残る本を書きたいんです」。よくそう言っていた。
彼女は『編集者 国木田独歩の時代』で角川財団学芸賞を受賞している。本格的に書き始めてからの短い時間に、それもノンフィクションの分野で、これだけの実績を納めたのだから、すごいとしか言いようがない。本当に、これからの活躍が期待されていた友だちだった。
黒岩さんの人柄はブログを読めばわかる。
その一つひとつが命を削った作品になってしまった。幸いなことに、彼女のブログは、彼女の志と共に、友人たちがずっと大切に受け継いでいる。
彼女の最後のブログ(下記のアドレス)もそのまま残っている。読むのは辛い。だが、ときどき開いて、笑顔が似合う、元気なときの黒岩ちゃんに会いたくなる。
http://blog.livedoor.jp/hisako9618/archives/2010-10.html
いつものように100円の文庫本コーナーの背表紙を、ア行の作者の名前からワ行までたどるように見ていく。
いま売れているらしい作家たちの本の多いこと。それも新刊ピカピカがズラリ。こんなにどんどん出版して、売れない在庫の山を次々に古本業界にまわして、出版界は大丈夫だろうか。
本もまたモノとして、すっかり消耗品になったらしい。ということは、作家も消耗品になったのだろうか。その勢いはますます加速しているような気がしてならない。
取り立てて、買いたい本はない。人だかりしているマンガコーナーを横目に、さっさと店を出た。
学生時代に親しんだ古本屋には、歴史を重ねた古本屋ならではの落ち着いた味わいがあった。大学に通う大通りの左右には、小は間口2間ほどから、大は4、5間ほどの古本屋が並んでいて、ガラス窓の奥の飾り棚には「××全集」、「××選集」の分厚い本の束がいくつも積まれていた。
カネが入ったら、あの全集を買ってやるぞ。そうおもいながらも、ついに実現しなかった。それらの全集の束を見つめていた学生はぼくだけではなかった。
古本屋で手にした本の巻末のページには、見ず知らずの先輩諸兄のサインや読後の一文が書き込まれていたり、蔵書版が押されている本もあった。
こうして一冊の本がぼくの手に来るまでの道のりを想像するだけでも、知的な興奮を覚えたものだ。田舎者のぼくにとって、学生街の古本屋は「これから知る教養」との出会いの場だった。
ずっと読み継がれている本は、自分も読まなければとおもい、専門書の棚の前ではその測り知れない学問の奥の深さに圧倒され、いま話題の新刊書を見つけると、シメタとおもった。
古本と言えば、亡くなった友人のノンフィクション作家・黒岩比佐子さんのことを想い出す。彼女のブログ『古書の森日記 by Hisaco』には多くのファンがついていた。
ひところ福岡市内で暮らしていて、一緒に仕事をしたこともある。狭い自宅にも来てくれた。出身地の東京に戻ってからは、福岡に来るたびに、ぼくの事務所に立ち寄って、帰りの飛行機の時刻いっぱいまで、彼女が書いている原稿の話で盛り上がった。贈ってくれた本はいまも手元においている。
彼女のことはとても軽々しく書けない。
最後の作品になった『パンとペン 社会主義者・堺利彦と「売文社」の闘い』の発行は2010年10月7日。彼女がすい臓ガンで亡くなったのは翌11月17日。その後で、読売文学賞「評論・伝記賞」が受与された。
福岡にいたころに着想を得た処女作『音のない記憶 ろうあの天才 写真家井之上孝治の生涯』も、『「食道楽」の人 村井弦斎』(サントリー学芸賞)も、無名の彼女が自分の意思で書きあげた原稿を持って、出版社を飛び込みでまわって、それぞれ文芸春秋と岩波書店の編集者から認められて出版された。
いま、そんな書き手がどれほどいるだろうか。
五木寛之氏からの信頼も厚く、彼の『百寺巡礼』の詳細な資料を集めて、書きやすく整理したのも黒岩さんである。慶應義塾では女子ソフトテニス部のキャプテンをして、そちらの方でも大活躍された。
「キャプテンだから、がんばらないと。ランニングでも、どんなにきつくても、絶対に先頭を走っていました」と言っていた。
飾らず、威張らず、地道に、コツコツと励み、体力の限界まで、ベストを尽くす人だった。一日中、国会図書館もこもって、吐きそうになるのを我慢して、古い新聞のマイクロフィルムを読み漁っていたと聞いたこともある。取材で海外にも足を伸ばしていた。あれほど徹底的に調べあげる人に会ったことがない。
黒岩さんが亡くなったのは52歳。
「子どものころから、いつか自分の本を書きたいというのが夢でした。わたしが死んでも、一冊でもいいから、ずっと後まで残る本を書きたいんです」。よくそう言っていた。
彼女は『編集者 国木田独歩の時代』で角川財団学芸賞を受賞している。本格的に書き始めてからの短い時間に、それもノンフィクションの分野で、これだけの実績を納めたのだから、すごいとしか言いようがない。本当に、これからの活躍が期待されていた友だちだった。
黒岩さんの人柄はブログを読めばわかる。
その一つひとつが命を削った作品になってしまった。幸いなことに、彼女のブログは、彼女の志と共に、友人たちがずっと大切に受け継いでいる。
彼女の最後のブログ(下記のアドレス)もそのまま残っている。読むのは辛い。だが、ときどき開いて、笑顔が似合う、元気なときの黒岩ちゃんに会いたくなる。
http://blog.livedoor.jp/hisako9618/archives/2010-10.html
カラス、なぜ鳴くの ― 2021年04月26日 16時32分

買いもの帰りの道すがら、一羽のカラスが細長い枝のようなものを咥えて、萌黄色の若葉がそよぐ銀杏並木の上を飛んでいった。きっと巣づくりに忙しいのだろう。いまは繁殖期のまっただなかである。
4、5年前の梅雨が始まるころ、ぼくはカラスの夫婦に執念ぶかく、つけ狙われたことがある。嘴(くちばし)が太くて、先っぽが湾曲しているハシブトガラスだった。
その日、自宅のそばの小路を歩いていると、突然、背後から大きな黒い影がぼくの頭をかすめるように越えて行った。そいつは10メートルほど先の街灯のてっぺんに止まると、ピョンと小さく跳ねて、からだごと振り返り、「カアー」と力いっぱい鳴いたのである。
瞬間、こいつ、俺を狙ったんだ、と確信した。
それからの毎日、カラスの攻撃は執拗に続いた。自宅から外に出たとたん、二つの黒い点が上空に現れて、カアー、カアーと鳴きながら、戦闘機のように猛スピードで接近してくる。歩いているとうるさくつきまとう。車で出かけるときも、途中まで追いかけてきた。
たいていは目の前のマンションの屋上や電柱、電線のどこかにいて、自宅の窓のカーテンをちょっと揺らすだけで、たちまちボリュームいっぱいのカアー、カアー、がはじまった。そして、ガッ、ガッ、ガッ、と鋭い嘴を突き立てる威嚇行動を繰り返すのだ。徹底的に無視して振り向いたら、2メートル足らずの至近距離まで迫られていたこともあった。
これなら感づかれないだろうと傘で上半身を隠しても、洋服を替えても、カラスはひと目で見破った。音を立てないように玄関のドアを開けてもダメだった。
遠くから眺めているだけで、どうして瞬時にわかるのだろうか。せめてもの救いは、ターゲットはぼくだけで、家族にはいっさい関心を示さないことだった。
なぜ、こんなことになってしまったのか。思い当たることはひとつだけあった。
あるとき幼いカラスが自宅下の階段のわきにいた。小首をかしげて、横目でじっとぼくを見上げたまま動こうとしない。まだ人をこわがっていないようだった。そこは人が出入りするところなので、ほら、あっちに行けと、軽く脚をふりだして追いはらった。
カラスの子は地面すれすれをゆっくり羽ばたいて、7、8メートルほど飛んだ。そちちはぼくが歩いていく方向だったので、もう一度、追いたてる恰好になった。
たったそれだけのことだった。だが、カラスのにぎやかな鳴き声がいつも間近で聞こえるようになったのは、どうもそのへんからだったような気がする。
あまりのしつこさに、ぼくは外に出るのが嫌になった。大きな声でのべつまくなしに、カアー、カアー騒がれると、近所の人たちも不審におもうかもしれない。それだけは避けたかった。
頭にきたぼくは、カラスになんかに負けてたまるかとあれこれ撃退法を考えた。10通り以上も考えた撃退法は省略するが、いつか友だちに一部始終を話したことがある。
すると、予想もしない答えが返ってきた。
「やっつけたい気持ちはわかるけど、やめた方がいい。虐待をしていると騒がれて、鳥獣保護法違反で訴えられるよ」
オー・マイ・ゴッド! そうだった、彼らは法律で身の安全を守られているのだ。なんたる不条理。人間よりも、おカラス様の方がお大事ということか。ゴム銃でお撃ちすることも、お生け捕りすることも、法律違反に問われるのだ。
それにしてしても、とおもう。平穏な生活は本人の意思とは関係なく、ほんのちょっとした偶然の出来事で、あっけなくかき乱されてしまう。あのときカラスの子どもが、あの場所で遊んでいなかったら、こんなことにはならなかった。
もしもあのとき、あの道を通っていなかったら。ネコが飛び出してこなかったら。突風さえ吹かなかったら……。振り返ると、そんなことだらけである。
ぼくは「潮の目」が変わるのを、じっと我慢して待つことにした。
9月になったある朝、あのうっとうしいカラスの夫婦はこつ然と姿を消していた。ようやく子育て中心の家族生活を終えて、山の方で集団生活をはじめたようだった。
翌日も、次の日も、黒い怪物は視界から完全にいなくなった。今まで悪い夢でも見ていたようだった。ぼくは安心して見上げる空を、久々に取り戻したのである。
カラスの親は子どもをしっかり見守っている。あのときも近くにいたのだ。やっと飛べるようになったばかりのわが子を追い払ったぼくを見て、アイツは危険な敵だとマークしたのだろう。きっとそうに違いない。
まるで人の心を読みきったような、あんなに頭のいいカラスには会ったことがない。今度会うときにはケンカしないで、仲良くなりたいのだが、まわりにいる黒いカラスの中の、どれがあのカラスなのか、ぼくにはさっぱり見分けがつかないのである。
4、5年前の梅雨が始まるころ、ぼくはカラスの夫婦に執念ぶかく、つけ狙われたことがある。嘴(くちばし)が太くて、先っぽが湾曲しているハシブトガラスだった。
その日、自宅のそばの小路を歩いていると、突然、背後から大きな黒い影がぼくの頭をかすめるように越えて行った。そいつは10メートルほど先の街灯のてっぺんに止まると、ピョンと小さく跳ねて、からだごと振り返り、「カアー」と力いっぱい鳴いたのである。
瞬間、こいつ、俺を狙ったんだ、と確信した。
それからの毎日、カラスの攻撃は執拗に続いた。自宅から外に出たとたん、二つの黒い点が上空に現れて、カアー、カアーと鳴きながら、戦闘機のように猛スピードで接近してくる。歩いているとうるさくつきまとう。車で出かけるときも、途中まで追いかけてきた。
たいていは目の前のマンションの屋上や電柱、電線のどこかにいて、自宅の窓のカーテンをちょっと揺らすだけで、たちまちボリュームいっぱいのカアー、カアー、がはじまった。そして、ガッ、ガッ、ガッ、と鋭い嘴を突き立てる威嚇行動を繰り返すのだ。徹底的に無視して振り向いたら、2メートル足らずの至近距離まで迫られていたこともあった。
これなら感づかれないだろうと傘で上半身を隠しても、洋服を替えても、カラスはひと目で見破った。音を立てないように玄関のドアを開けてもダメだった。
遠くから眺めているだけで、どうして瞬時にわかるのだろうか。せめてもの救いは、ターゲットはぼくだけで、家族にはいっさい関心を示さないことだった。
なぜ、こんなことになってしまったのか。思い当たることはひとつだけあった。
あるとき幼いカラスが自宅下の階段のわきにいた。小首をかしげて、横目でじっとぼくを見上げたまま動こうとしない。まだ人をこわがっていないようだった。そこは人が出入りするところなので、ほら、あっちに行けと、軽く脚をふりだして追いはらった。
カラスの子は地面すれすれをゆっくり羽ばたいて、7、8メートルほど飛んだ。そちちはぼくが歩いていく方向だったので、もう一度、追いたてる恰好になった。
たったそれだけのことだった。だが、カラスのにぎやかな鳴き声がいつも間近で聞こえるようになったのは、どうもそのへんからだったような気がする。
あまりのしつこさに、ぼくは外に出るのが嫌になった。大きな声でのべつまくなしに、カアー、カアー騒がれると、近所の人たちも不審におもうかもしれない。それだけは避けたかった。
頭にきたぼくは、カラスになんかに負けてたまるかとあれこれ撃退法を考えた。10通り以上も考えた撃退法は省略するが、いつか友だちに一部始終を話したことがある。
すると、予想もしない答えが返ってきた。
「やっつけたい気持ちはわかるけど、やめた方がいい。虐待をしていると騒がれて、鳥獣保護法違反で訴えられるよ」
オー・マイ・ゴッド! そうだった、彼らは法律で身の安全を守られているのだ。なんたる不条理。人間よりも、おカラス様の方がお大事ということか。ゴム銃でお撃ちすることも、お生け捕りすることも、法律違反に問われるのだ。
それにしてしても、とおもう。平穏な生活は本人の意思とは関係なく、ほんのちょっとした偶然の出来事で、あっけなくかき乱されてしまう。あのときカラスの子どもが、あの場所で遊んでいなかったら、こんなことにはならなかった。
もしもあのとき、あの道を通っていなかったら。ネコが飛び出してこなかったら。突風さえ吹かなかったら……。振り返ると、そんなことだらけである。
ぼくは「潮の目」が変わるのを、じっと我慢して待つことにした。
9月になったある朝、あのうっとうしいカラスの夫婦はこつ然と姿を消していた。ようやく子育て中心の家族生活を終えて、山の方で集団生活をはじめたようだった。
翌日も、次の日も、黒い怪物は視界から完全にいなくなった。今まで悪い夢でも見ていたようだった。ぼくは安心して見上げる空を、久々に取り戻したのである。
カラスの親は子どもをしっかり見守っている。あのときも近くにいたのだ。やっと飛べるようになったばかりのわが子を追い払ったぼくを見て、アイツは危険な敵だとマークしたのだろう。きっとそうに違いない。
まるで人の心を読みきったような、あんなに頭のいいカラスには会ったことがない。今度会うときにはケンカしないで、仲良くなりたいのだが、まわりにいる黒いカラスの中の、どれがあのカラスなのか、ぼくにはさっぱり見分けがつかないのである。
ベランダの幸せ・桑の実 ― 2021年04月27日 12時19分

「あーっ、おしいかった。三つ、食べちゃった」
狭いベランダから、カミさんの明るい声が聞こえた。ペタペタとサンダルの音がして、「ほら、お父さんもどうぞ」と手の平を差し出した。
黒いつぶつぶの実が五つ、のっかっている。桑の実である。ことしは実のつくのが早かった。
ぶどうの実を何十分の一も縮小したように、黒い真珠みたいな小さな玉がぎっしりくっついている。定規ではかってみると、サイズは16ミリ×11ミリだった。五個を一度にまとめて食べても、イチゴ一個分にもならない。
だが、ぼくにとって桑の実の価値は、イチゴの何倍も大きい。それは思い出の値打ちである。
桑の実が色づくころ、ぼくがいた鹿児島の田舎町では、よく近所の兄ちゃんたちと相撲をとっていた。遊び仲間の小学生たちが集まって、地元の祭りの六月灯(ロッガッドーと呼んでいた)のビッグイベントだった相撲大会の練習をするのだ。
町中の人たちが待ちわびていた六月灯の日、ぼくたちは大人が萱(かや)を刈り取って、手づくりしてくれたひと抱えもある重たい綱を曳いて、ワッショイ、ワッショイと通りを練り歩き、錦江湾に面した浜辺まで運んで行った。萱の太い綱は砂でこしらえた土俵を円(まる)くかこむ俵になった。
まわりにはイカを焼く匂い、綿菓子の甘い香り、セルロイドでできた月光仮面やハリマオの面、ヨーヨー釣りなどの出店が立ち並び、あたりいったいは煌々と照らされて、昼間のようだった。
両親や町内の人、同級生の女の子たちも注目するなかで、ぼくたち男の子は、かごんま(鹿児島)の男のメンツを賭けて、勝ち抜き戦の相撲をとるのだ。優勝賞品はノートと鉛筆だった。
ぼくたちの年齢で優勝するのは、下駄屋の次男坊の「とっどん」に決まっていた。いちばんの仲良しで、ふたりで山に入って遊んでいたとき、彼は足を踏み外して、ゴロゴロ転がり落ちて、右腕を折ったことがある。
成績もクラスで一番だった。高校三年のとき、合格間違いなしと言われた東大が学園紛争で入試中止となり、「とっどん」はそのことで新聞に載ったことがある。日本の端っこの田舎町にも、あんなスターがいた。
桑の実から話は脱線してしまったが、日暮れまで夢中で相撲をとって、おやつ代わりに食べたのが、すぐ近くにあった桑の実だった。口の中が真っ黒になって、みんなで見せ合い、大笑いしたことがなつかしい。
「新潟では桑の実のことを、桑イチゴと言ってた。わたしが子どもころ、うちの家は蚕を飼っていたから、よく桑の葉をあげたね。雨が降っているような音をたてて、ムシャムシャ食べるのよね」
こちらはカミさんの子ども時代の思い出。働き者だったひいおばあちゃんは「かいこおんな」と呼ばれていたという。桑の木も、桑の実も、いろんな思い出のある人が全国各地に大勢いるのだろう。
ベランダの桑の木は高さ80センチほど。四方に伸びた枝が邪魔になったので、以前、カミさんは新潟の姉に、「なつかしいでしょ。車で持って行こうか」と提案したことがあった。
返事は「桑の木なんて、珍しくもない。この間、伐ったばっかりだよ。そんなもの要らないよ」だった。
黒い宝石のような実を口に入れると、野イチゴのような香りと甘く濃い味が広がる。鉄筋コンクリート造りの公団住宅にいるぼくの気持ちは決まっている。
絶対に、やらんもんね。
狭いベランダから、カミさんの明るい声が聞こえた。ペタペタとサンダルの音がして、「ほら、お父さんもどうぞ」と手の平を差し出した。
黒いつぶつぶの実が五つ、のっかっている。桑の実である。ことしは実のつくのが早かった。
ぶどうの実を何十分の一も縮小したように、黒い真珠みたいな小さな玉がぎっしりくっついている。定規ではかってみると、サイズは16ミリ×11ミリだった。五個を一度にまとめて食べても、イチゴ一個分にもならない。
だが、ぼくにとって桑の実の価値は、イチゴの何倍も大きい。それは思い出の値打ちである。
桑の実が色づくころ、ぼくがいた鹿児島の田舎町では、よく近所の兄ちゃんたちと相撲をとっていた。遊び仲間の小学生たちが集まって、地元の祭りの六月灯(ロッガッドーと呼んでいた)のビッグイベントだった相撲大会の練習をするのだ。
町中の人たちが待ちわびていた六月灯の日、ぼくたちは大人が萱(かや)を刈り取って、手づくりしてくれたひと抱えもある重たい綱を曳いて、ワッショイ、ワッショイと通りを練り歩き、錦江湾に面した浜辺まで運んで行った。萱の太い綱は砂でこしらえた土俵を円(まる)くかこむ俵になった。
まわりにはイカを焼く匂い、綿菓子の甘い香り、セルロイドでできた月光仮面やハリマオの面、ヨーヨー釣りなどの出店が立ち並び、あたりいったいは煌々と照らされて、昼間のようだった。
両親や町内の人、同級生の女の子たちも注目するなかで、ぼくたち男の子は、かごんま(鹿児島)の男のメンツを賭けて、勝ち抜き戦の相撲をとるのだ。優勝賞品はノートと鉛筆だった。
ぼくたちの年齢で優勝するのは、下駄屋の次男坊の「とっどん」に決まっていた。いちばんの仲良しで、ふたりで山に入って遊んでいたとき、彼は足を踏み外して、ゴロゴロ転がり落ちて、右腕を折ったことがある。
成績もクラスで一番だった。高校三年のとき、合格間違いなしと言われた東大が学園紛争で入試中止となり、「とっどん」はそのことで新聞に載ったことがある。日本の端っこの田舎町にも、あんなスターがいた。
桑の実から話は脱線してしまったが、日暮れまで夢中で相撲をとって、おやつ代わりに食べたのが、すぐ近くにあった桑の実だった。口の中が真っ黒になって、みんなで見せ合い、大笑いしたことがなつかしい。
「新潟では桑の実のことを、桑イチゴと言ってた。わたしが子どもころ、うちの家は蚕を飼っていたから、よく桑の葉をあげたね。雨が降っているような音をたてて、ムシャムシャ食べるのよね」
こちらはカミさんの子ども時代の思い出。働き者だったひいおばあちゃんは「かいこおんな」と呼ばれていたという。桑の木も、桑の実も、いろんな思い出のある人が全国各地に大勢いるのだろう。
ベランダの桑の木は高さ80センチほど。四方に伸びた枝が邪魔になったので、以前、カミさんは新潟の姉に、「なつかしいでしょ。車で持って行こうか」と提案したことがあった。
返事は「桑の木なんて、珍しくもない。この間、伐ったばっかりだよ。そんなもの要らないよ」だった。
黒い宝石のような実を口に入れると、野イチゴのような香りと甘く濃い味が広がる。鉄筋コンクリート造りの公団住宅にいるぼくの気持ちは決まっている。
絶対に、やらんもんね。
ジョウショ君よ、いまどこにいる? ― 2021年04月30日 23時09分

あいつ、どうしているかな。
40年前、東京駅の新幹線改札口で別れた友の顔を思い浮かべている。正真正銘の文学青年だった。名前は、城処久志という。仮名にしたが、本人はもとより、彼を知っている人なら、ピンとくるだろう。
昨日、カミさんに尻を叩かれて、天袋に押し込んだままの収納ボックスを片づけた。するとB4サイズのファイルが出てきた。少し色あせたピンク、イエロー、ブルー、グリーンの表紙の分厚い4冊。
ファイルには400字詰め原稿用紙のコピーが合計596枚綴じられている。万年筆の黒インクで書かれた細かい文字がびっしり。旧字の漢字や仮名遣いの混じっているところが、いかにもあいつらしい。
書き直した跡がないので、推敲を何度も重ねた上で清書したことがわかる。一字一字を間違えないように書くのに一枚当たり20分かかるとして、ざっと12,000時間。一睡もしないで書き続けて500日かかった計算になる。そこに至るまでの下書きの時間を入れたら、いったいどれほどの労力を費やしたことか。
城処君は、ぼくがカミさんを連れて福岡市に転居する直前に、この4冊のファイルを携えて、ぼくらが暮らすアパートまでやってきた。
「このコピーを保管しておいてくれ。万一、俺の手元にある原稿が火事で燃えたりしたら、ぜんぶが無になってしまう。だから、たのむよ」
この未発表の論文のタイトルは「春秋左氏傳についての研究」。春秋左氏傳(略称・左伝)は紀元前の前漢末期に世に出たといわれる中国の古書で、孔子の編纂と伝えられる歴史書「春秋」の代表的な注釈書の一つである。
いまでは苦笑いするしかないが、学生時代に城処君の発案から仲のいい先輩を加えた三人で「左伝」の読書会をはじめた。講師は城処君、場所はぼくの四畳半のアパート、時間は毎週土曜日の夕方、読書会の後はそのまま部屋で一杯やることに決まった。
彼から教えられた神田神保町の中国書専門店で購入した「左伝」は、まさしく漢籍そのものだった。高校で使った教科書や参考書のように返り点など、どこにもついていない。文字はすべて旧字体で、文字の画数の多さにも辟易(へきえき)した。漢文の素養のない先輩もぼくも、これどうするのといった感じ。まるで固い岩盤に爪を立てるように、ぼう然として、なすすべなしだった。
そのむずかしい白文を、城処君は声を上げてすらすら読んでいく。登場人物や時代背景のことも併せて、一つひとつ解説するのである。
しかし、いくら教えてもらっても、まったくのお手上げで、先輩とぼくは二カ月足らずであっさり根を上げてしまった。
そういうぼくたちに比べると先人たちは偉い。かつての武士をはじめ、塾や寺子屋で勉強していた子どもたちは尊敬に値する。論語や孟子の漢文に親しみ、できる人は四書五経まで諳(そら)んじていたのだから。
ぼくが記者になった後も、城処君はよく遊びにきた。「左伝」に登場する人物の心理をどう理解すればいいのか、そういう話が多かった。ぼくは事件や政治の取材を通じて知った人間の欲望や葛藤の例を持ちだしては、ああだ、こうだと、人の心の動きに想像をめぐらしながら、「左伝」の解釈について意見を出し合うことがおもしろかった。
そのころ城処君は大望を抱いていた。それは「左伝」の訳文で主流派と言われていた京都大学の高名なK教授の学説を堂々と論破することだった。そして、彼はますます「左伝」の研究に没頭し、乾坤一擲の思いを込めた論文を書き上げて、ついにK教授の研究室に送ったのだ。
「原稿は送り返されてきたよ。K教授とは別名の人の短い感想の手紙も入っていたけど、俺の論点にちゃんと答えていない。ぜんぜん納得できん」
これが待ち焦がれていた回答だった。高く聳える壁にはね返されたわけだ。友の悔しさが晴れることはなかった。ぼくの手元にあるのが、まさしくその原稿のコピーである。
城処君のルーツは四国の松山で、生まれ育ちは大阪と言っていた。そのことは彼の自慢だった。
「おれには子規や漱石がいた四国の松山と、西鶴や近松が活躍した大阪の血が流れている。日本文学の王道の土地で育ったからな」
大学では日本文学研究の道に進んだが、「教授の話を聞いてもつまらん」と言って、一年で中退。なにしろ彼は読書の領域と量がケタ違いだった。中学生のときには毎月、中央公論を読んでいて、古典から名だたる作家の作品はたいてい読破していた。たとえば、ぼくが新潟県塩沢の鈴木牧之の名前を出すと、即座に「彼の書いた北越雪譜はいいよな」と言うのである。
そのうち彼は、もう漢文は卒業したと言って、今度はシェークスピアを〈原語〉で読み直していた。歌舞伎座で聴き覚えた人気役者の声色を使うのも得意だった。あれは活字中毒なんてものじゃない。からだじゅうに文学が詰まっているような男だった。
古本屋で本を買い込んで、読みだしたら二晩続けて徹夜して、一日に一度の飯は缶詰一個をおかずにして、鍋いっぱいに炊いた三合の米をあらたか食ってしまう。間借りしていた三畳の部屋はきちんと整理されていたが、「明るいと気が散るから」といつも暗くしていた。ぼくは「本の虫」という人間に初めて出会ったのだ。
よく徹夜して怒鳴り合うように議論した。野菜不足を解消するために、生の大根やキャベツをかじりながら、ふたりで大学の構内を歩いたこともある。
最後に会ったのは、ぼくが13年ぶりに九州で暮らすときだった。身長160数センチの細身のからだに、どこか太宰治をおもわせる顔立ち。別れ際に見せた城処君のいまにも泣き出しそうな顔が忘れられない。
友よ、元気でいるか。いつか君は世に出てくる人物だと、ぼくはいまでもおもっているよ。
40年前、東京駅の新幹線改札口で別れた友の顔を思い浮かべている。正真正銘の文学青年だった。名前は、城処久志という。仮名にしたが、本人はもとより、彼を知っている人なら、ピンとくるだろう。
昨日、カミさんに尻を叩かれて、天袋に押し込んだままの収納ボックスを片づけた。するとB4サイズのファイルが出てきた。少し色あせたピンク、イエロー、ブルー、グリーンの表紙の分厚い4冊。
ファイルには400字詰め原稿用紙のコピーが合計596枚綴じられている。万年筆の黒インクで書かれた細かい文字がびっしり。旧字の漢字や仮名遣いの混じっているところが、いかにもあいつらしい。
書き直した跡がないので、推敲を何度も重ねた上で清書したことがわかる。一字一字を間違えないように書くのに一枚当たり20分かかるとして、ざっと12,000時間。一睡もしないで書き続けて500日かかった計算になる。そこに至るまでの下書きの時間を入れたら、いったいどれほどの労力を費やしたことか。
城処君は、ぼくがカミさんを連れて福岡市に転居する直前に、この4冊のファイルを携えて、ぼくらが暮らすアパートまでやってきた。
「このコピーを保管しておいてくれ。万一、俺の手元にある原稿が火事で燃えたりしたら、ぜんぶが無になってしまう。だから、たのむよ」
この未発表の論文のタイトルは「春秋左氏傳についての研究」。春秋左氏傳(略称・左伝)は紀元前の前漢末期に世に出たといわれる中国の古書で、孔子の編纂と伝えられる歴史書「春秋」の代表的な注釈書の一つである。
いまでは苦笑いするしかないが、学生時代に城処君の発案から仲のいい先輩を加えた三人で「左伝」の読書会をはじめた。講師は城処君、場所はぼくの四畳半のアパート、時間は毎週土曜日の夕方、読書会の後はそのまま部屋で一杯やることに決まった。
彼から教えられた神田神保町の中国書専門店で購入した「左伝」は、まさしく漢籍そのものだった。高校で使った教科書や参考書のように返り点など、どこにもついていない。文字はすべて旧字体で、文字の画数の多さにも辟易(へきえき)した。漢文の素養のない先輩もぼくも、これどうするのといった感じ。まるで固い岩盤に爪を立てるように、ぼう然として、なすすべなしだった。
そのむずかしい白文を、城処君は声を上げてすらすら読んでいく。登場人物や時代背景のことも併せて、一つひとつ解説するのである。
しかし、いくら教えてもらっても、まったくのお手上げで、先輩とぼくは二カ月足らずであっさり根を上げてしまった。
そういうぼくたちに比べると先人たちは偉い。かつての武士をはじめ、塾や寺子屋で勉強していた子どもたちは尊敬に値する。論語や孟子の漢文に親しみ、できる人は四書五経まで諳(そら)んじていたのだから。
ぼくが記者になった後も、城処君はよく遊びにきた。「左伝」に登場する人物の心理をどう理解すればいいのか、そういう話が多かった。ぼくは事件や政治の取材を通じて知った人間の欲望や葛藤の例を持ちだしては、ああだ、こうだと、人の心の動きに想像をめぐらしながら、「左伝」の解釈について意見を出し合うことがおもしろかった。
そのころ城処君は大望を抱いていた。それは「左伝」の訳文で主流派と言われていた京都大学の高名なK教授の学説を堂々と論破することだった。そして、彼はますます「左伝」の研究に没頭し、乾坤一擲の思いを込めた論文を書き上げて、ついにK教授の研究室に送ったのだ。
「原稿は送り返されてきたよ。K教授とは別名の人の短い感想の手紙も入っていたけど、俺の論点にちゃんと答えていない。ぜんぜん納得できん」
これが待ち焦がれていた回答だった。高く聳える壁にはね返されたわけだ。友の悔しさが晴れることはなかった。ぼくの手元にあるのが、まさしくその原稿のコピーである。
城処君のルーツは四国の松山で、生まれ育ちは大阪と言っていた。そのことは彼の自慢だった。
「おれには子規や漱石がいた四国の松山と、西鶴や近松が活躍した大阪の血が流れている。日本文学の王道の土地で育ったからな」
大学では日本文学研究の道に進んだが、「教授の話を聞いてもつまらん」と言って、一年で中退。なにしろ彼は読書の領域と量がケタ違いだった。中学生のときには毎月、中央公論を読んでいて、古典から名だたる作家の作品はたいてい読破していた。たとえば、ぼくが新潟県塩沢の鈴木牧之の名前を出すと、即座に「彼の書いた北越雪譜はいいよな」と言うのである。
そのうち彼は、もう漢文は卒業したと言って、今度はシェークスピアを〈原語〉で読み直していた。歌舞伎座で聴き覚えた人気役者の声色を使うのも得意だった。あれは活字中毒なんてものじゃない。からだじゅうに文学が詰まっているような男だった。
古本屋で本を買い込んで、読みだしたら二晩続けて徹夜して、一日に一度の飯は缶詰一個をおかずにして、鍋いっぱいに炊いた三合の米をあらたか食ってしまう。間借りしていた三畳の部屋はきちんと整理されていたが、「明るいと気が散るから」といつも暗くしていた。ぼくは「本の虫」という人間に初めて出会ったのだ。
よく徹夜して怒鳴り合うように議論した。野菜不足を解消するために、生の大根やキャベツをかじりながら、ふたりで大学の構内を歩いたこともある。
最後に会ったのは、ぼくが13年ぶりに九州で暮らすときだった。身長160数センチの細身のからだに、どこか太宰治をおもわせる顔立ち。別れ際に見せた城処君のいまにも泣き出しそうな顔が忘れられない。
友よ、元気でいるか。いつか君は世に出てくる人物だと、ぼくはいまでもおもっているよ。
最近のコメント