波当津の海に会う ― 2021年05月06日 10時37分

波当津の海に会ってきた。
大分県の海岸線を南にたどっていくと宮崎県にはいる。その手前にある小村が波当津だ。現在の世帯数は70戸足らず、人口は140人ほど。小学校はとっくの昔に廃校になった。店は一軒もない。絵に描いたような過疎地だが、ここは亡き母の郷里である。
8年前の2013年2月、こんな陸の孤島に東九州自動車道の蒲江波当津ICが開設された。しかも、佐伯ICから延岡南ICの区間の通行料金は年中無料。日中でも車の通行量は少なく、ハンドルを握っていると、まるで高速道路を貸しきっているような気分になる。
なぜ、こんなところにインターチェンジができたのか、詳しい事情は知らないが、思いがけない用地提供で大金が入った人たちにとっては夢のような出来事だった。ただ高速道路の出入り口はできたものの、過疎化の歯止めにはなっていない。
このあたりは大小の岬が陸続と豊後水道に突き出している。ほかにも山塊が海の方へ出っ張ったところや沖に浮かぶ小島や岩礁は数え切れないほどあって、ここは日本有数のリアス式海岸が望めるところである。
岬と岬の間の深く切り込んだ湾に点在する村を浦(うら)と呼ぶ。波当津もかつては波当津浦が正式な地名だった。浦には、人が密集しているところもあれば、無人の浜もある。
蒲江町出身の作家・小野正嗣さんの著書「にぎやかな湾に背負われた船」を手にしたとき、さすがにうまいタイトルをつけるものだと感心した。
中学、高校、一浪時代、東京の大学に進んでからも、ぼくは夏休みになるとひとりで波当津に行った。祖父の家に2、3週間も泊まり込んで、毎日のように若い叔父や従兄たちと一緒に沖の瀬で遊ぶのだ。
波のかたまりが瀬に近づくとみるみる巨大な水の凸レンズになって、水面下にある岩や海藻がグワーッと拡大されて盛り上がる。波が通りすぎるとそれらは見る間に沈んでいく。
キラキラと青く光る熱帯魚の群れや大きなサザエ、いろんな巻貝がいて、みんなでぼくの遊びの相手をしてくれた。そこは生きている海だった。叔父は手製の銛(もり)を手に、船から飛び込むとそのまま深く潜って、上がってくるときには大きなイガメ(ブダイのこと)を突いていた。
いまとは違って、村も元気だった。どの家も年寄りと子どもたちがひとつ屋根の下で暮らしていて、道を歩いていると「また遊びに来たんかよー」と、あちこちから声がかかってくる。明るく陽気な村だった。
写真は、古い堤防に立って、宮崎方面の外海を写したもの。左へのびている岬をまわったところが県境の宇土崎だ。その突端には波や風で削りとられた大きな穴が開いている。そこをくぐり抜けると宮崎県で、小さな公園のような入り江がある。
地元では「猫が浜」と呼んでいる。名前の由来は、たしかネコの額ほどしかない浜、という意味だったとおもう。すぐ後ろは見上げるような絶壁で、とても歩いて来れるところではない。
透明度の高い波当津の海でも、砂地のない「猫が浜」の水はとりわけ澄み切っていて、水中メガネをつけて潜ると、海の中とはおもえないほど遠い先まで見えた。
ぼくが伝馬船の櫓を押して、結婚して間もないカミさんをここまで連れてきたことがある。テーブルサンゴ、色とりどりの魚たち、いろんな貝類は、雪国育ちの彼女にとって珍しいものばかり。カミさんは長い棒を使って、ムラサキウニを獲るのに夢中になっていた。
波当津の海は、ぼくのとっておきの楽園だった。そう、浪人生のころまでは。
東京に出て、大学がはじまってすぐのちょうどこの時期、大好きだった若い叔父が事故で命を落とした。29歳だった。翌年には兄弟のようだった23歳の従兄も事故死した。叔父は3人の幼い子どもたちを残し、従兄はかわいい婚約者を置き去りにした。
こうして波当津のたのしい思い出はあっけなく最盛期を過ぎてしまった。
従兄の葬式が終わった秋口の夜、ひとりで浜まで歩いて行った。台風が近づいている海は大しけで、真っ暗な闇から波の砕ける音が風と共に吹きつけてきた。まるで「波」が「当」たる「津」の素顔をむきだしにしているようだった。
ぼくは素っ裸になって、ワーッと叫びながら、冷たい波の中に頭から飛び込んだ。黒くて塩辛い水の壁が何度も、何度もぶち当たってきた。あのときどうして、あんな激情が腹の底から込み上げてきたのか、自分でもわからなかった。
先日、何年ぶりかで会った海は、当時のようにきれいだった。だが、この村で暮らしている弟分の従兄によると、海は変わってしまったという。
ぼくたちの言う海とは、海の中のことである。岩場から海藻の類がすっかり消えてしまったというのだ。海藻がなければ貝も魚も棲めない。全国的な問題になっている「磯焼け」は、こんな田舎まで広がっていた。波当津の海は、何もいない海になってしまった。
知り合いの宗像大社のA宮司によると、世界遺産の沖ノ島周辺の海底にはそれまでなかったサンゴ礁が群生しているという。いつの間にか、日本海の孤島の環境は南の海の島になっていた。もっと水温の高い波当津の海が無事でいられるわけがなかったのだ。
ぼくに何ができるだろうか。思い出すのは、作家の北村薫さんが「作家の履歴書」の中で書いていた次の文章である。
-昭和初期の学生たちをとりまく人間模様、私がそのうちに入って物語を紡がなければ消えてしまう世界を読めるかたちにして出していくのが、作家としての自分の責任、書かなければいけないものだと感じています-
「消えてしまうことを書く」。これなら、ぼくにもできるかもしれない。
波当津の浜から土産を持って帰った。浜辺に転がっていた小石を三つ。いま机に上に置いてある。ぼくの耳には、打ち寄せる波でまるく削られた石ころから、あのなつかしい潮騒が聞こえてくる。
大分県の海岸線を南にたどっていくと宮崎県にはいる。その手前にある小村が波当津だ。現在の世帯数は70戸足らず、人口は140人ほど。小学校はとっくの昔に廃校になった。店は一軒もない。絵に描いたような過疎地だが、ここは亡き母の郷里である。
8年前の2013年2月、こんな陸の孤島に東九州自動車道の蒲江波当津ICが開設された。しかも、佐伯ICから延岡南ICの区間の通行料金は年中無料。日中でも車の通行量は少なく、ハンドルを握っていると、まるで高速道路を貸しきっているような気分になる。
なぜ、こんなところにインターチェンジができたのか、詳しい事情は知らないが、思いがけない用地提供で大金が入った人たちにとっては夢のような出来事だった。ただ高速道路の出入り口はできたものの、過疎化の歯止めにはなっていない。
このあたりは大小の岬が陸続と豊後水道に突き出している。ほかにも山塊が海の方へ出っ張ったところや沖に浮かぶ小島や岩礁は数え切れないほどあって、ここは日本有数のリアス式海岸が望めるところである。
岬と岬の間の深く切り込んだ湾に点在する村を浦(うら)と呼ぶ。波当津もかつては波当津浦が正式な地名だった。浦には、人が密集しているところもあれば、無人の浜もある。
蒲江町出身の作家・小野正嗣さんの著書「にぎやかな湾に背負われた船」を手にしたとき、さすがにうまいタイトルをつけるものだと感心した。
中学、高校、一浪時代、東京の大学に進んでからも、ぼくは夏休みになるとひとりで波当津に行った。祖父の家に2、3週間も泊まり込んで、毎日のように若い叔父や従兄たちと一緒に沖の瀬で遊ぶのだ。
波のかたまりが瀬に近づくとみるみる巨大な水の凸レンズになって、水面下にある岩や海藻がグワーッと拡大されて盛り上がる。波が通りすぎるとそれらは見る間に沈んでいく。
キラキラと青く光る熱帯魚の群れや大きなサザエ、いろんな巻貝がいて、みんなでぼくの遊びの相手をしてくれた。そこは生きている海だった。叔父は手製の銛(もり)を手に、船から飛び込むとそのまま深く潜って、上がってくるときには大きなイガメ(ブダイのこと)を突いていた。
いまとは違って、村も元気だった。どの家も年寄りと子どもたちがひとつ屋根の下で暮らしていて、道を歩いていると「また遊びに来たんかよー」と、あちこちから声がかかってくる。明るく陽気な村だった。
写真は、古い堤防に立って、宮崎方面の外海を写したもの。左へのびている岬をまわったところが県境の宇土崎だ。その突端には波や風で削りとられた大きな穴が開いている。そこをくぐり抜けると宮崎県で、小さな公園のような入り江がある。
地元では「猫が浜」と呼んでいる。名前の由来は、たしかネコの額ほどしかない浜、という意味だったとおもう。すぐ後ろは見上げるような絶壁で、とても歩いて来れるところではない。
透明度の高い波当津の海でも、砂地のない「猫が浜」の水はとりわけ澄み切っていて、水中メガネをつけて潜ると、海の中とはおもえないほど遠い先まで見えた。
ぼくが伝馬船の櫓を押して、結婚して間もないカミさんをここまで連れてきたことがある。テーブルサンゴ、色とりどりの魚たち、いろんな貝類は、雪国育ちの彼女にとって珍しいものばかり。カミさんは長い棒を使って、ムラサキウニを獲るのに夢中になっていた。
波当津の海は、ぼくのとっておきの楽園だった。そう、浪人生のころまでは。
東京に出て、大学がはじまってすぐのちょうどこの時期、大好きだった若い叔父が事故で命を落とした。29歳だった。翌年には兄弟のようだった23歳の従兄も事故死した。叔父は3人の幼い子どもたちを残し、従兄はかわいい婚約者を置き去りにした。
こうして波当津のたのしい思い出はあっけなく最盛期を過ぎてしまった。
従兄の葬式が終わった秋口の夜、ひとりで浜まで歩いて行った。台風が近づいている海は大しけで、真っ暗な闇から波の砕ける音が風と共に吹きつけてきた。まるで「波」が「当」たる「津」の素顔をむきだしにしているようだった。
ぼくは素っ裸になって、ワーッと叫びながら、冷たい波の中に頭から飛び込んだ。黒くて塩辛い水の壁が何度も、何度もぶち当たってきた。あのときどうして、あんな激情が腹の底から込み上げてきたのか、自分でもわからなかった。
先日、何年ぶりかで会った海は、当時のようにきれいだった。だが、この村で暮らしている弟分の従兄によると、海は変わってしまったという。
ぼくたちの言う海とは、海の中のことである。岩場から海藻の類がすっかり消えてしまったというのだ。海藻がなければ貝も魚も棲めない。全国的な問題になっている「磯焼け」は、こんな田舎まで広がっていた。波当津の海は、何もいない海になってしまった。
知り合いの宗像大社のA宮司によると、世界遺産の沖ノ島周辺の海底にはそれまでなかったサンゴ礁が群生しているという。いつの間にか、日本海の孤島の環境は南の海の島になっていた。もっと水温の高い波当津の海が無事でいられるわけがなかったのだ。
ぼくに何ができるだろうか。思い出すのは、作家の北村薫さんが「作家の履歴書」の中で書いていた次の文章である。
-昭和初期の学生たちをとりまく人間模様、私がそのうちに入って物語を紡がなければ消えてしまう世界を読めるかたちにして出していくのが、作家としての自分の責任、書かなければいけないものだと感じています-
「消えてしまうことを書く」。これなら、ぼくにもできるかもしれない。
波当津の浜から土産を持って帰った。浜辺に転がっていた小石を三つ。いま机に上に置いてある。ぼくの耳には、打ち寄せる波でまるく削られた石ころから、あのなつかしい潮騒が聞こえてくる。
室見川にアユが戻ってきた ― 2021年05月11日 14時41分

コロナウィルス感染者が過去最多。明日12日からはまた緊急事態措置。
いい加減、うんざりする。政府の対応にもストレスがたまる。政治家が話す言葉の信用はとっくに地に堕ちた。個人攻撃はしたくないが、このところの日本の政治のトップリーダーは教養を積んでいる人ではない。そんな彼らに従わざるをえない、高い志を持った優秀な官僚たちはバカバカしくてやっていられないだろう。
あの言語学者の金田一秀穂さんは、ある雑誌でこう憤慨している。
-この政権(安倍政権)について、なによりも、言葉の扱いの粗雑さが我慢ならない。国語の勉強を全然していない。漢字を読めないし、語の意味も間違って覚えている。決定的に困るのは、それを恥と思っている様子がほとんどないことなのだ。勉強のできない学生の典型的な態度で、無知であること、蒙昧(もうまい)であることが何より恥ずべきことであると、全然思っていないかのようである。
ふつう、大学を出て、それになりの地位を占める人になるのであれば、自分が身につけてきた基礎教養を振り返り、間違えないようにしよう、正しく言葉を使っていこうと決意するだろうとおもうのだが、二人のAさんは、一向にそのように見えない。今までにない政治が出現している。何も信じられない。聞いているだけで気持ちが悪くなる-
ふたりのAさん(大臣)がだれなのか、言われなくてもわかる。そして、いまの政権もまったく同じ延長線上にあるとおもっているのは、ぼくだけではないだろう。
ここまで書いて、切りがないから止める。以下は、散歩から帰って、気分を入れ替えて書き足した。
こういうときは外に出るに限る。若葉の真っ盛りで、木々の葉っぱは艶やかに輝き、五月の薫風のなかで精気を放っている。足は自然と室見川へ向かった。
もう稚アユがのぼっているはず。川辺の遊歩道からそっと見下ろすと、狭い浅瀬のあちこちで、サーッ小さなさざ波が広がった。
いる、いる。体長5、6センチほどの小魚の群れ。アユの子たちが海から戻ってきた。
むろん、養殖モノでも、放流モノでもない。天然のアユである。これから上流へと遡っていき、川底の石についたコケを食(は)んで大きくなる。やがて銀色の光をギラリと反射しながら、水中を矢のように走る立派なアユになる。
梅雨が明けるとアユの群れを狙って、投網を打つ人も出て来る。ぼくはこの川で、釣り糸に釣り針を鈴なりに結んで、アユを引っ掛けたことがある。そろそろ毛バリを流して、ハヤ釣りも楽しめる。でも、そういう川遊びをする大人はすっかりいなくなった。だから、子どもたちもそういう漁(りょう)の技を学びようがない。
海もそうだが、川でもおもしろいのは水の中だ。そこは陸上とは別の世界がある。
カミさんの新潟の郷里はアユ釣りのメッカの魚野川とその支流が何本も流れていて、どの川にもアユやヤマメがいる。
ある夏、ぼくは水量の多い魚野川にまだ小学生だった息子二人を連れて行って、アユの手づかみをやってみせたことがある。
やり方は簡単だ。腰の下ほどの深さの川の中に立って、両手で軽く持ち上げられるぐらいの石を探す。それを高く掲げて、力いっぱい水の中に叩き込む。これを連続して何回もやる。そして、間髪を容(い)れずに水中メガネをつけて、川の中を見るのだ。
すると、石がぶつかった衝撃波に驚いたアユが川底の石と石のすき間にピタッと張りついたまま動かないでいることがある。そいつをそっと手で押し包むようにすればいい。道具も要らない。まったくの素手ひとつで、泳ぎまわっていたアユはわがものになるという寸法である。
川の流れを横目に歩きながら、憂うつなコロナのことも、頭にくる政治家のことも消し飛んで、ぼくはそんなことを考えていた。
やっぱり、自然はいい。ああ、室見川が近くにあってよかった。
いい加減、うんざりする。政府の対応にもストレスがたまる。政治家が話す言葉の信用はとっくに地に堕ちた。個人攻撃はしたくないが、このところの日本の政治のトップリーダーは教養を積んでいる人ではない。そんな彼らに従わざるをえない、高い志を持った優秀な官僚たちはバカバカしくてやっていられないだろう。
あの言語学者の金田一秀穂さんは、ある雑誌でこう憤慨している。
-この政権(安倍政権)について、なによりも、言葉の扱いの粗雑さが我慢ならない。国語の勉強を全然していない。漢字を読めないし、語の意味も間違って覚えている。決定的に困るのは、それを恥と思っている様子がほとんどないことなのだ。勉強のできない学生の典型的な態度で、無知であること、蒙昧(もうまい)であることが何より恥ずべきことであると、全然思っていないかのようである。
ふつう、大学を出て、それになりの地位を占める人になるのであれば、自分が身につけてきた基礎教養を振り返り、間違えないようにしよう、正しく言葉を使っていこうと決意するだろうとおもうのだが、二人のAさんは、一向にそのように見えない。今までにない政治が出現している。何も信じられない。聞いているだけで気持ちが悪くなる-
ふたりのAさん(大臣)がだれなのか、言われなくてもわかる。そして、いまの政権もまったく同じ延長線上にあるとおもっているのは、ぼくだけではないだろう。
ここまで書いて、切りがないから止める。以下は、散歩から帰って、気分を入れ替えて書き足した。
こういうときは外に出るに限る。若葉の真っ盛りで、木々の葉っぱは艶やかに輝き、五月の薫風のなかで精気を放っている。足は自然と室見川へ向かった。
もう稚アユがのぼっているはず。川辺の遊歩道からそっと見下ろすと、狭い浅瀬のあちこちで、サーッ小さなさざ波が広がった。
いる、いる。体長5、6センチほどの小魚の群れ。アユの子たちが海から戻ってきた。
むろん、養殖モノでも、放流モノでもない。天然のアユである。これから上流へと遡っていき、川底の石についたコケを食(は)んで大きくなる。やがて銀色の光をギラリと反射しながら、水中を矢のように走る立派なアユになる。
梅雨が明けるとアユの群れを狙って、投網を打つ人も出て来る。ぼくはこの川で、釣り糸に釣り針を鈴なりに結んで、アユを引っ掛けたことがある。そろそろ毛バリを流して、ハヤ釣りも楽しめる。でも、そういう川遊びをする大人はすっかりいなくなった。だから、子どもたちもそういう漁(りょう)の技を学びようがない。
海もそうだが、川でもおもしろいのは水の中だ。そこは陸上とは別の世界がある。
カミさんの新潟の郷里はアユ釣りのメッカの魚野川とその支流が何本も流れていて、どの川にもアユやヤマメがいる。
ある夏、ぼくは水量の多い魚野川にまだ小学生だった息子二人を連れて行って、アユの手づかみをやってみせたことがある。
やり方は簡単だ。腰の下ほどの深さの川の中に立って、両手で軽く持ち上げられるぐらいの石を探す。それを高く掲げて、力いっぱい水の中に叩き込む。これを連続して何回もやる。そして、間髪を容(い)れずに水中メガネをつけて、川の中を見るのだ。
すると、石がぶつかった衝撃波に驚いたアユが川底の石と石のすき間にピタッと張りついたまま動かないでいることがある。そいつをそっと手で押し包むようにすればいい。道具も要らない。まったくの素手ひとつで、泳ぎまわっていたアユはわがものになるという寸法である。
川の流れを横目に歩きながら、憂うつなコロナのことも、頭にくる政治家のことも消し飛んで、ぼくはそんなことを考えていた。
やっぱり、自然はいい。ああ、室見川が近くにあってよかった。
スイッチを入れる ― 2021年05月19日 15時23分
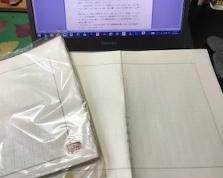
行動開始のスイッチを入れるため、散歩がてらダイソーに行った。目当ては400字詰めの原稿用紙。少し迷った末に、B4サイズの35枚入りとA4サイズ50枚入りをそれぞれ1組ずつ購入した。これぐらいは買っておかねば。いまから、どんどん書くのだから。
パソコンでは原稿を書いている気がしない。いまもこうしてパソコンに向かっているけれど、原稿を書くというよりも、ボタンをたたいているという感じである。
手で書く習慣がなくなると、どんどん語句や漢字を忘れてしまう。鴎外や荷風、潤一郎たちの小説に出てくる小粋で、簡潔で、味のある言葉ともすっかり縁遠くなった。久世光彦の著書「ニホンゴキトク」の対象はぼくのことだった。
あるNPO法人の手伝いをしていたとき、地元のホームページ制作会社の幹部からこう言われたことがある。30歳ちょっと過ぎで、「デキル男」と言われている人だった。
「××さんの文章は、まるでホンモノの記者が書いたみたいじゃないですか。それじゃあ、若い人たちから読んでもらえませんよ。いまは素人が書いたような、ヘタな文章の方がいいんですよ」
面と向かって、そう言われて絶句した。そして、こういう人がインターネットの文章の書き方を指導しているという現実を知った。パソコンやスマホのキーボードを指先でチョコチョコ打ちながら作る文章とニホンゴキトクには、深い相関関係がありそうだ。
話がヨコ道にそれてしまった。
そうなのだ、原稿を書こうというスイッチを入れるために、ぼくは原稿用紙を買ったのだ。あれは串田孫一だったか、はっきりとは覚えていないが、こんなことを言っていた。
ワープロで文章を書いて、書き直すときに、その文章はボタンひとつで、パッと全部消えてしまう。一生懸命考えてきた文章が何も残らない。でも、原稿用紙に書いて、消して、また書き直す場合は、いままで何を書いていたか、何を考えていたかが記憶としても、手の感触としても残る。その感覚を大切にしたい。だからワープロは使ってみたけれど、すぐ止めた。
言いたいことはよくわかる。実際に鉛筆を使って、原稿用紙に書いている作家もいる。気合いのスイッチを入れるためには、やっぱり原稿用紙に文字を一つひとつ書かなくては。
買ってきた原稿用紙をどこに置こうかと、机のまわりの収納箱を整理していたら、奥の方から「COOP」のマーク入りの値札を貼られたビニール袋が三つ出てきた。なかには400字詰めの原稿用紙の束が入っている。値段はA4サイズ、20枚で90円。ずいぶん昔の物価である。
COOPと言えば、学生時代に校内にあった大学生協しか思い当たるところはない。まっさらな原稿用紙を広げて見たら、なんと、それにはわが母校の大学名が印刷されているではないか。
ということは、50年近く前にも、いまと同じように「さぁ、原稿を書くぞ」とスイッチを入れて、衝動的に買ったに違いない。まさしく、これが動かぬ証拠である。
思えば、「よし、やるぞ」とスイッチを入れては熱く燃え上がり、やがてその情熱は徐々に下火となって、ついには消え果て、忘れたころにまた思い直して、スイッチを入れてきた。
さて、今度はどうか。前夜の禁酒の誓いも、夕刻になると前言撤回してばかり。
何も書かれていない新旧の原稿用紙の束を前にして、すでにぼくはだんだんやる気を失いかけている。ああ、もう一度、最初からスイッチを入れなくては。
パソコンでは原稿を書いている気がしない。いまもこうしてパソコンに向かっているけれど、原稿を書くというよりも、ボタンをたたいているという感じである。
手で書く習慣がなくなると、どんどん語句や漢字を忘れてしまう。鴎外や荷風、潤一郎たちの小説に出てくる小粋で、簡潔で、味のある言葉ともすっかり縁遠くなった。久世光彦の著書「ニホンゴキトク」の対象はぼくのことだった。
あるNPO法人の手伝いをしていたとき、地元のホームページ制作会社の幹部からこう言われたことがある。30歳ちょっと過ぎで、「デキル男」と言われている人だった。
「××さんの文章は、まるでホンモノの記者が書いたみたいじゃないですか。それじゃあ、若い人たちから読んでもらえませんよ。いまは素人が書いたような、ヘタな文章の方がいいんですよ」
面と向かって、そう言われて絶句した。そして、こういう人がインターネットの文章の書き方を指導しているという現実を知った。パソコンやスマホのキーボードを指先でチョコチョコ打ちながら作る文章とニホンゴキトクには、深い相関関係がありそうだ。
話がヨコ道にそれてしまった。
そうなのだ、原稿を書こうというスイッチを入れるために、ぼくは原稿用紙を買ったのだ。あれは串田孫一だったか、はっきりとは覚えていないが、こんなことを言っていた。
ワープロで文章を書いて、書き直すときに、その文章はボタンひとつで、パッと全部消えてしまう。一生懸命考えてきた文章が何も残らない。でも、原稿用紙に書いて、消して、また書き直す場合は、いままで何を書いていたか、何を考えていたかが記憶としても、手の感触としても残る。その感覚を大切にしたい。だからワープロは使ってみたけれど、すぐ止めた。
言いたいことはよくわかる。実際に鉛筆を使って、原稿用紙に書いている作家もいる。気合いのスイッチを入れるためには、やっぱり原稿用紙に文字を一つひとつ書かなくては。
買ってきた原稿用紙をどこに置こうかと、机のまわりの収納箱を整理していたら、奥の方から「COOP」のマーク入りの値札を貼られたビニール袋が三つ出てきた。なかには400字詰めの原稿用紙の束が入っている。値段はA4サイズ、20枚で90円。ずいぶん昔の物価である。
COOPと言えば、学生時代に校内にあった大学生協しか思い当たるところはない。まっさらな原稿用紙を広げて見たら、なんと、それにはわが母校の大学名が印刷されているではないか。
ということは、50年近く前にも、いまと同じように「さぁ、原稿を書くぞ」とスイッチを入れて、衝動的に買ったに違いない。まさしく、これが動かぬ証拠である。
思えば、「よし、やるぞ」とスイッチを入れては熱く燃え上がり、やがてその情熱は徐々に下火となって、ついには消え果て、忘れたころにまた思い直して、スイッチを入れてきた。
さて、今度はどうか。前夜の禁酒の誓いも、夕刻になると前言撤回してばかり。
何も書かれていない新旧の原稿用紙の束を前にして、すでにぼくはだんだんやる気を失いかけている。ああ、もう一度、最初からスイッチを入れなくては。
魚売り場の女のひと ― 2021年05月21日 18時48分

おや、引っ越したとばかりおもっていたが、そうじゃなかったんだ。
先日の夕方、カミさんと自宅近くの小路を歩いていたら、前方から小柄な女性がやってきた。
ん? 見覚えのある顔立ち。数メートル先からのまっすぐな視線とぶつかって、お互いに笑みがもれた。
「やぁ、お久しぶり。お元気ですか」
「はい。わたしのこと覚えています?」
「もちろんですよ。で、いま、どちらにお勤めですか」
「天神のお店でレジをしています」
ずいぶん日本語が上手になっていた。2年前に閉店したすぐ近くのスーパーの鮮魚売り場で、パートなのに、それこそ身を粉にするようにして働いていた人である。
あのころは長い髪を後ろにゴムで束ねて、頭には白いスカーフをかぶり、白の調理服、足元は黒い長靴というスタイル。見たところは30代の前半で、丸い顔には愛嬌があって、ちゃんと化粧をすれば、評判になってもおかしくないようなかわいい人である。
毎朝、6時にはぼくの住まいの下の道を通り過ぎて行った。駐車場に停めている軽トラックを運転して、魚の仕入れに向かうのだ。
店が開くのは午前9時半。彼女は鮮魚コーナーの調理場のなかで、大きな包丁を右手に握って、次々と大小の魚をさばいていく。客からの魚の下処理の注文もこなす。切り身も刺身もどんどん作っていく。店の中でいちばん忙しく働いているのが、いつも魚と格闘している彼女だった。
「さぁ、いらっしゃい。今日は鯛がお買い得ですよ。鯛が安いよー」
売り声も威勢がいい。さぼっているところを見たことがない。大きなまな板に水道の水をジャブジャブ掛け流して、足元は魚のウロコや内臓のカケラが混じった汚水でビチャビチャだ。きっと魚のニオイが身体じゅうに染みついて、いわゆるセレブの世界とかけ離れた境遇にあることは明らかだった。
お腹が大きくふくらんで、母親になっても、仕事を長く休んでいたという記憶がない。たどたどしい話し方や胸につけていた名札の苗字から、彼女が日本人ではないことはだれもが知っていた。
スーパーの閉店と共に、彼女はいなくなった。歩いている姿もまったく見かけなくなった。てっきりどこかへ引っ越していったとおもっていた。久しぶりに会ってわかったのは、彼女が通勤に利用するバス亭は、ぼくの住まいとは反対の方向だったのだ。
口を利くのは2年ぶりだった。あの長靴を履いたスタイルではなく、ふつうに街へ出かける身だしなみで、笑顔も、口ぶりも、しばらく会っていなかった距離を感じさせない。カミさんも顔見知りなので、うれしそうだった。
「ホント、お久しぶりですね。魚屋さんで、すごくがんばっていたでしょ」
「もう魚屋の仕事は嫌です。あれは本当にきつかったです。二度とやりたくありません」
「でも、せっかく技術を身につけたのにねぇ」
「ものすごくつらかったです。お店がなくなって、辞めることができてよかったです。もう、絶対にやりません」
ぼくも、カミさんも、初めて彼女の本音を聞いた。あんなに仕事に打ち込んでいた人だったのに、心の中は真逆だったのだ。そんなにきつくて、つらい仕事だったのか。
「あのときはお世話になりました。これからも、よろしくお願いします」
ピョコンと頭を下げて、こちらまで明るくなるような声だった。
「ええ、こちらこそ。よかった、お元気そうで」
ほんの1、2分だったが、コロナ禍の中で、久々に気持ちのいい会話をした。
こういう人こそ最後には笑ってほしい。与えられた場所でコツコツとがんばる人。嫌になったら、簡単に辞めてしまうぼくとは大違いである。
レジの仕事は、おそらく魚を扱っていたときよりも安い報酬だろう。そこでも嫌なことはいっぱいあるだろうに、以前よりもずっといいという。ひと昔前は、こんな女の人は珍しくなかった。
いまも元気でやっていることがわかって、なんだかぼくまでうれしくなった。彼女と率直な話をして、生まれ育った国こそ違っても、家族のために辛抱強くがんばる母親像にふれたような気がしたのである。
■魚屋さんはなくてはならない存在だ。魚の目利きの確かさや鮮やかな包丁さばきにはあこがれを感じる。ほかのスーパーにも魚売り場で生き生きと働いている女性たちがいる。ちなみに、ぼくの息子は和食の料理人で、毎日、嫌というほど魚をさばいている。
■写真は波当津の浜辺。手前は石ころだらけだが、すぐ先から砂浜が広がっている。子どもころ、男たちは潜って大きなハマグリを獲っていた。その場で焼いて、食べさせてもらうのがうれしかった。
先日の夕方、カミさんと自宅近くの小路を歩いていたら、前方から小柄な女性がやってきた。
ん? 見覚えのある顔立ち。数メートル先からのまっすぐな視線とぶつかって、お互いに笑みがもれた。
「やぁ、お久しぶり。お元気ですか」
「はい。わたしのこと覚えています?」
「もちろんですよ。で、いま、どちらにお勤めですか」
「天神のお店でレジをしています」
ずいぶん日本語が上手になっていた。2年前に閉店したすぐ近くのスーパーの鮮魚売り場で、パートなのに、それこそ身を粉にするようにして働いていた人である。
あのころは長い髪を後ろにゴムで束ねて、頭には白いスカーフをかぶり、白の調理服、足元は黒い長靴というスタイル。見たところは30代の前半で、丸い顔には愛嬌があって、ちゃんと化粧をすれば、評判になってもおかしくないようなかわいい人である。
毎朝、6時にはぼくの住まいの下の道を通り過ぎて行った。駐車場に停めている軽トラックを運転して、魚の仕入れに向かうのだ。
店が開くのは午前9時半。彼女は鮮魚コーナーの調理場のなかで、大きな包丁を右手に握って、次々と大小の魚をさばいていく。客からの魚の下処理の注文もこなす。切り身も刺身もどんどん作っていく。店の中でいちばん忙しく働いているのが、いつも魚と格闘している彼女だった。
「さぁ、いらっしゃい。今日は鯛がお買い得ですよ。鯛が安いよー」
売り声も威勢がいい。さぼっているところを見たことがない。大きなまな板に水道の水をジャブジャブ掛け流して、足元は魚のウロコや内臓のカケラが混じった汚水でビチャビチャだ。きっと魚のニオイが身体じゅうに染みついて、いわゆるセレブの世界とかけ離れた境遇にあることは明らかだった。
お腹が大きくふくらんで、母親になっても、仕事を長く休んでいたという記憶がない。たどたどしい話し方や胸につけていた名札の苗字から、彼女が日本人ではないことはだれもが知っていた。
スーパーの閉店と共に、彼女はいなくなった。歩いている姿もまったく見かけなくなった。てっきりどこかへ引っ越していったとおもっていた。久しぶりに会ってわかったのは、彼女が通勤に利用するバス亭は、ぼくの住まいとは反対の方向だったのだ。
口を利くのは2年ぶりだった。あの長靴を履いたスタイルではなく、ふつうに街へ出かける身だしなみで、笑顔も、口ぶりも、しばらく会っていなかった距離を感じさせない。カミさんも顔見知りなので、うれしそうだった。
「ホント、お久しぶりですね。魚屋さんで、すごくがんばっていたでしょ」
「もう魚屋の仕事は嫌です。あれは本当にきつかったです。二度とやりたくありません」
「でも、せっかく技術を身につけたのにねぇ」
「ものすごくつらかったです。お店がなくなって、辞めることができてよかったです。もう、絶対にやりません」
ぼくも、カミさんも、初めて彼女の本音を聞いた。あんなに仕事に打ち込んでいた人だったのに、心の中は真逆だったのだ。そんなにきつくて、つらい仕事だったのか。
「あのときはお世話になりました。これからも、よろしくお願いします」
ピョコンと頭を下げて、こちらまで明るくなるような声だった。
「ええ、こちらこそ。よかった、お元気そうで」
ほんの1、2分だったが、コロナ禍の中で、久々に気持ちのいい会話をした。
こういう人こそ最後には笑ってほしい。与えられた場所でコツコツとがんばる人。嫌になったら、簡単に辞めてしまうぼくとは大違いである。
レジの仕事は、おそらく魚を扱っていたときよりも安い報酬だろう。そこでも嫌なことはいっぱいあるだろうに、以前よりもずっといいという。ひと昔前は、こんな女の人は珍しくなかった。
いまも元気でやっていることがわかって、なんだかぼくまでうれしくなった。彼女と率直な話をして、生まれ育った国こそ違っても、家族のために辛抱強くがんばる母親像にふれたような気がしたのである。
■魚屋さんはなくてはならない存在だ。魚の目利きの確かさや鮮やかな包丁さばきにはあこがれを感じる。ほかのスーパーにも魚売り場で生き生きと働いている女性たちがいる。ちなみに、ぼくの息子は和食の料理人で、毎日、嫌というほど魚をさばいている。
■写真は波当津の浜辺。手前は石ころだらけだが、すぐ先から砂浜が広がっている。子どもころ、男たちは潜って大きなハマグリを獲っていた。その場で焼いて、食べさせてもらうのがうれしかった。
四つ葉のクローバーがいっぱい ― 2021年05月25日 19時09分

何かいいことがあるかもしれない。
団地の中のあちこちに緑色のクローバーがじゅうたんのように広がって、白い花の帽子をつけている。ふと、四つ葉のクローバーって、あったよな、と子どものころをおもいだした。二つ違いの姉と何本見つけるか、競争したっけ。
しゃがみこんで、目を凝らす。ひとつ、見つけた。ふたつがならんでいるのも見つかった。四つ葉のクローバーはめったにないというけれど、探せばわりとあるものだ。
そのうち写真の場所に行きあたった。四つ葉のクローバーが左、真ん中、その右下にも、そして右側にもある。ところが、よく見たら、右側のクローバーは五つ葉だった。10センチ四方ほどのところに、四つ葉が三つ、五つ葉がひとつ。これってかなり珍しいことではないだろうか。まるで幸運が肩を寄せ合っているみたいではないか。
さて、ぼくの希少な目撃体験といえば、最たるものは鹿児島の田舎町にいたときのこと。小学3、4年生のころだった。
鉄道官舎の裏の原っぱで、ひとりで赤とんぼの群れと遊んでいたとき、かすかに赤ん坊が泣いているような音が聞こえた。赤ちゃんなんて、どこの家にもいないのに、何だろうと泣き声のする方向へ歩いて行った。ネコもニワトリもいない。でも、たしかに聞いたことのない、喉を締めつけられたような泣き声がする。それも地面の草むらの方から。
何か動いているような気配を感じて、足元の土で汚れたズックを見た。そのすぐ先で灰色の細いヒモがクネクネと左右に振れている。瞬間、身体じゅうに鳥肌が立ち、おもわず立ちすくんでしまった。
小さなヘビのしっぽだった。しっぽの根元は緑と茶色が混じった、これも小さなカエルの口の中に消えていた。
カエルはじっとしていて、どうしていいのかわからないようだった。とても全部を呑み込める相手ではない。かといって、吐き出すこともできないようだった。ぼくはじっと二匹の様子を眺めていた。どちらが殺すか、殺されるか。
きっと最後はヘビが勝つだろうとおもった。アマガエルのようなカエルはもうそれ以上、口をあけることもできず、息遣いをするたびに赤ちゃんのような悲鳴を上げていた。ああ、殺(や)られるのは、お前のほうだなとおもった。そして、その最後の結末は見たくなかった。
夕食の席で、小さなカエルがヘビの子どもの頭を呑み込んでいたと父に話した。父はさほど驚きもせず、「ヘビに睨まれたカエルというけれど、カエルも必死だからね。そういうことがあるんだよ」という返事だった。
父は山でマムシをつかまえて、家の近くの川でその頭を切りおとして、サーッとウロコのついた皮をはぐのもへっちゃらだった。秋の山では桜の木に近づくなと教えられた。そこには桜の木肌の模様に似た冬眠前のマムシがよく隠れているのだ。実際に葉を落としたヤマザクラの木の根元で大きなマムシに出くわしたこともある。
そういう父が言うのだから、カエルがヘビの頭を咥え込んでいたことも、ふーんと納得したのである。
あのころは「窮鼠(きゅうそ)、猫を噛む」というむずかしい格言を知らなかった。でも、そういう大人の社会の言葉は知らなくても、あんな小さな生き物にも、絶体絶命に追い詰められたら、命懸けで反撃してやる、という生存本能があることは、実際にその現場を見たので、よくわかった。
ふだん意識することはないが、きっとぼくにも、あのカエルとヘビの死闘から感じとった同じ動物の本能がどこかにくっついているのだろう。いままで何度も、もうどうしようもないという窮地に立たされてきたが、そのたびに「これぐらいのことで」と乗り越えてきたような気がする。
幸運をもたらすという四つ葉のクローバーをいくつも見つけたことが、きっと草むらの中の事件という連想につながって、あのカエルとヘビの格闘シーンをおもいだしたのだろう。話してもなかなか信じてもらえない、ふつうは一生見ることもないであろう、あの珍しいシーンにたまたま出会えたことも、考えようによっては「運がよかった」と言えるのかもしれない。
団地の中のあちこちに緑色のクローバーがじゅうたんのように広がって、白い花の帽子をつけている。ふと、四つ葉のクローバーって、あったよな、と子どものころをおもいだした。二つ違いの姉と何本見つけるか、競争したっけ。
しゃがみこんで、目を凝らす。ひとつ、見つけた。ふたつがならんでいるのも見つかった。四つ葉のクローバーはめったにないというけれど、探せばわりとあるものだ。
そのうち写真の場所に行きあたった。四つ葉のクローバーが左、真ん中、その右下にも、そして右側にもある。ところが、よく見たら、右側のクローバーは五つ葉だった。10センチ四方ほどのところに、四つ葉が三つ、五つ葉がひとつ。これってかなり珍しいことではないだろうか。まるで幸運が肩を寄せ合っているみたいではないか。
さて、ぼくの希少な目撃体験といえば、最たるものは鹿児島の田舎町にいたときのこと。小学3、4年生のころだった。
鉄道官舎の裏の原っぱで、ひとりで赤とんぼの群れと遊んでいたとき、かすかに赤ん坊が泣いているような音が聞こえた。赤ちゃんなんて、どこの家にもいないのに、何だろうと泣き声のする方向へ歩いて行った。ネコもニワトリもいない。でも、たしかに聞いたことのない、喉を締めつけられたような泣き声がする。それも地面の草むらの方から。
何か動いているような気配を感じて、足元の土で汚れたズックを見た。そのすぐ先で灰色の細いヒモがクネクネと左右に振れている。瞬間、身体じゅうに鳥肌が立ち、おもわず立ちすくんでしまった。
小さなヘビのしっぽだった。しっぽの根元は緑と茶色が混じった、これも小さなカエルの口の中に消えていた。
カエルはじっとしていて、どうしていいのかわからないようだった。とても全部を呑み込める相手ではない。かといって、吐き出すこともできないようだった。ぼくはじっと二匹の様子を眺めていた。どちらが殺すか、殺されるか。
きっと最後はヘビが勝つだろうとおもった。アマガエルのようなカエルはもうそれ以上、口をあけることもできず、息遣いをするたびに赤ちゃんのような悲鳴を上げていた。ああ、殺(や)られるのは、お前のほうだなとおもった。そして、その最後の結末は見たくなかった。
夕食の席で、小さなカエルがヘビの子どもの頭を呑み込んでいたと父に話した。父はさほど驚きもせず、「ヘビに睨まれたカエルというけれど、カエルも必死だからね。そういうことがあるんだよ」という返事だった。
父は山でマムシをつかまえて、家の近くの川でその頭を切りおとして、サーッとウロコのついた皮をはぐのもへっちゃらだった。秋の山では桜の木に近づくなと教えられた。そこには桜の木肌の模様に似た冬眠前のマムシがよく隠れているのだ。実際に葉を落としたヤマザクラの木の根元で大きなマムシに出くわしたこともある。
そういう父が言うのだから、カエルがヘビの頭を咥え込んでいたことも、ふーんと納得したのである。
あのころは「窮鼠(きゅうそ)、猫を噛む」というむずかしい格言を知らなかった。でも、そういう大人の社会の言葉は知らなくても、あんな小さな生き物にも、絶体絶命に追い詰められたら、命懸けで反撃してやる、という生存本能があることは、実際にその現場を見たので、よくわかった。
ふだん意識することはないが、きっとぼくにも、あのカエルとヘビの死闘から感じとった同じ動物の本能がどこかにくっついているのだろう。いままで何度も、もうどうしようもないという窮地に立たされてきたが、そのたびに「これぐらいのことで」と乗り越えてきたような気がする。
幸運をもたらすという四つ葉のクローバーをいくつも見つけたことが、きっと草むらの中の事件という連想につながって、あのカエルとヘビの格闘シーンをおもいだしたのだろう。話してもなかなか信じてもらえない、ふつうは一生見ることもないであろう、あの珍しいシーンにたまたま出会えたことも、考えようによっては「運がよかった」と言えるのかもしれない。
人をこわがらないスズメたち ― 2021年05月27日 11時02分

いま、団地の中は小さな命が躍動している。なかでも朝早くから元気がいいのはスズメの子たちである。
5月のはじめごろから姿をあらわして、ほんの数メートルをパタパタパタと飛んで、危なっかしく地面に降りる。ヨチヨチ歩きを始めた赤ちゃんみたいで、こちらがスタートダッシュすれば、すぐにも捕まえられそうだ。
わが家のまわりを飛びまわっているスズメの子どもたちの棲み処(か)は、自転車置き場の屋根の下。そこには屋根を支える三角形の鉄のパイプがわずかな傾斜をつけて架けられていて、三角の形の中はこぶし大の空洞になっている。その奥の方にスズメの巣があって、毎年この季節になると、この三角の穴から子スズメたちは飛び立つのである。
次男が小学校の低学年のころ、クラスの友だちとこの屋根の上によじ登って、ドン、ドン、ドンと飛び上がりながらダンスをやったことがやる。そしたら子スズメたちが大慌てで飛び出して、そのまま地面に墜落したという。スズメにすれば、雷と大地震が同時にやってきたような衝撃だったのだろう。
この時期はカラスの子どもたちも飛んでいる。そして、それを見守っている親ガラスにはスズメの子どもを襲うやつもいる。カラスはスズメの天敵なのだ。
地面で遊んでいるとネコにも警戒しなければいけない。世間の荒波を知らない無邪気な子スズメたちにとって、生きていくのは容易ではない。
スズメはこちらが近づくと、パッと逃げる。その昔、人間に獲って食われたという悪夢の体験が受け継がれているのだろうか、スズメは生まれたときから人を寄せつけないものだとおもっていた。
「おもっていた」と過去形で書いたのは、そうでもないスズメがいることを、ぼくは知っているからである。
人をこわがらないスズメたちは東京大学のある建物の中の学生サロンにいた。
そのころ、ぼくは地元の零細ベンチャー企業に関係していて、東大工学部の某准教授との間で結ばれた共同研究を進めるために、二か月に一度のペースで本郷のキャンパスに通っていた。地元のベンチャーが開発したユニークな加工素材の効用について、東大の研究機関からのエビデンス(科学的な証拠)を獲得し、併せて販路を開拓することが目的だった。
ある日、福岡から東京への日帰りの旅にくたびれて、大きな樹木がうっそうと繁る広いキャンパスで少し休もうと、学生サロンに置いてある椅子に座り込んだ。
すると、そこにいたスズメたちがチョン、チョン、チョンと両足ジャンプをしながら寄ってきたのだ。
3メートル、2メートル、1メートル。それでもまだ近づいてくる。50センチ、30センチ、10センチ。2羽が3羽になり、5羽、6羽になった。まるで保育園で遊んでいる子どもたちがワイワイと集まってきたようだった。
様子を見ていると、どうやらエサをくれるとおもっているらしい。小首をかしげて、かわいい目をパチパチしながら、こちらを見上げている。
ぼくは、このときほどパンを持っていなかったことを悔やんだことはない。それほど彼らは友好的だった。
休んでいたサロンのすぐ近くには、あの安田記念講堂があった。学生たちが立てこもって、機動隊と激しい攻防戦があったのは、ぼくが高校3年のとき。その影響で、ぼくたちの世代は東大の入試が中止になった。足元でチョコチョコ歩いている小さなスズメたちを見ていると、あのときの騒ぎがウソのようだった。
東大との共同研究は最終的にこちらの求める形にすることはできなかったが、ぼくは見ず知らずの人間をこわがらずに歓迎してくれた、あのスズメたちにもう一度、会いたくなる。
5月のはじめごろから姿をあらわして、ほんの数メートルをパタパタパタと飛んで、危なっかしく地面に降りる。ヨチヨチ歩きを始めた赤ちゃんみたいで、こちらがスタートダッシュすれば、すぐにも捕まえられそうだ。
わが家のまわりを飛びまわっているスズメの子どもたちの棲み処(か)は、自転車置き場の屋根の下。そこには屋根を支える三角形の鉄のパイプがわずかな傾斜をつけて架けられていて、三角の形の中はこぶし大の空洞になっている。その奥の方にスズメの巣があって、毎年この季節になると、この三角の穴から子スズメたちは飛び立つのである。
次男が小学校の低学年のころ、クラスの友だちとこの屋根の上によじ登って、ドン、ドン、ドンと飛び上がりながらダンスをやったことがやる。そしたら子スズメたちが大慌てで飛び出して、そのまま地面に墜落したという。スズメにすれば、雷と大地震が同時にやってきたような衝撃だったのだろう。
この時期はカラスの子どもたちも飛んでいる。そして、それを見守っている親ガラスにはスズメの子どもを襲うやつもいる。カラスはスズメの天敵なのだ。
地面で遊んでいるとネコにも警戒しなければいけない。世間の荒波を知らない無邪気な子スズメたちにとって、生きていくのは容易ではない。
スズメはこちらが近づくと、パッと逃げる。その昔、人間に獲って食われたという悪夢の体験が受け継がれているのだろうか、スズメは生まれたときから人を寄せつけないものだとおもっていた。
「おもっていた」と過去形で書いたのは、そうでもないスズメがいることを、ぼくは知っているからである。
人をこわがらないスズメたちは東京大学のある建物の中の学生サロンにいた。
そのころ、ぼくは地元の零細ベンチャー企業に関係していて、東大工学部の某准教授との間で結ばれた共同研究を進めるために、二か月に一度のペースで本郷のキャンパスに通っていた。地元のベンチャーが開発したユニークな加工素材の効用について、東大の研究機関からのエビデンス(科学的な証拠)を獲得し、併せて販路を開拓することが目的だった。
ある日、福岡から東京への日帰りの旅にくたびれて、大きな樹木がうっそうと繁る広いキャンパスで少し休もうと、学生サロンに置いてある椅子に座り込んだ。
すると、そこにいたスズメたちがチョン、チョン、チョンと両足ジャンプをしながら寄ってきたのだ。
3メートル、2メートル、1メートル。それでもまだ近づいてくる。50センチ、30センチ、10センチ。2羽が3羽になり、5羽、6羽になった。まるで保育園で遊んでいる子どもたちがワイワイと集まってきたようだった。
様子を見ていると、どうやらエサをくれるとおもっているらしい。小首をかしげて、かわいい目をパチパチしながら、こちらを見上げている。
ぼくは、このときほどパンを持っていなかったことを悔やんだことはない。それほど彼らは友好的だった。
休んでいたサロンのすぐ近くには、あの安田記念講堂があった。学生たちが立てこもって、機動隊と激しい攻防戦があったのは、ぼくが高校3年のとき。その影響で、ぼくたちの世代は東大の入試が中止になった。足元でチョコチョコ歩いている小さなスズメたちを見ていると、あのときの騒ぎがウソのようだった。
東大との共同研究は最終的にこちらの求める形にすることはできなかったが、ぼくは見ず知らずの人間をこわがらずに歓迎してくれた、あのスズメたちにもう一度、会いたくなる。
一発、逆転を祈る ― 2021年05月28日 19時18分

人は見たくないことから目をそらしたがるものだ。日本の近未来の現実を突きつけるこんな数字も、その典型的な事例だろう。
厚生労働省の発表によると、全国の自治体が2020年の1年間に受理した妊娠届の件数は前年比4・8%減の87万2227件で、過去最少を更新した。そのため21年の出生数は80万人を割り込み、70万人台になることが濃厚という。
減少の原因はまたしてもコロナウィルスにあるらしい。感染拡大による出産や子育ての不安から「妊娠控え」が起きたようだ、というのである。
理由はともあれ、とうとう1年間に生まれる子どもの数が80万人を切るという。実に恐るべき事態と言わざるをえない。
試みに、80万人のあかちゃんが大人になったとき、子どもの数がどうなるか、簡単な計算をしてみよう。
80万人のうち、男と女の割合が半々と仮定すると、女性の数は40万人。その全員が子どもを2人ずつ産むと80万人。これなら現状を維持できる。
しかし、それはまったく非現実的な話である。
いまでも30代後半の女性で未婚の人は全体の約3割もいる。この状況が将来も続くとしたら、女性40万人のうち、30代後半までに結婚する女性は、日本中でたった28万人しかいないことになる。これは福岡ソフトバンクホークスのホームゲームが満席で、わずか7試合やれば(合計観客数は26万9920人)、ほぼ到達する人数でしかない。
もちろん、結婚せずに子どもを育てるシングルマザーの人たちもいるだろうが、大勢には影響ないだろう。これでどうやって、わが国の人口を増やすというのだろうか。
もうひとつ、ぼくは人口減について、別の計算をしたことがある。
国の推計では、2065年の日本の人口は3,900万人も少なくなる。これは現在の大阪府より以西の中国、四国、九州・沖縄の全府県を合計した人口と同じ数である。つまり、来年生まれる子どもたちが43歳になったときには、いま大阪から西に住んでいる人口分がすっぽり消えてなくなっているのだ。あくまでも推計ではあるが。
もはや、想像を絶する日本の姿である。だが、このままではそうなってしまう。
このあたりのことを政府の発表はともかく、新聞やテレビは「少子高齢化社会」というお決まりの言葉ではなく、もっと身近に、わかりやすく、リアルに報道できないものかとおもう。
身につまされる話はぼくのまわりにもいっぱいある。自分の代で、家系が絶えてしまうという人がたくさんいるのだ。
子どもがいない。息子はいるけど、結婚する気もないし、相手もいない。養子になってくれる人なんていない。まだまだと言っている間に、適齢期を過ぎてしまった。本人も親も焦っているけど、まったくご縁がない。うちの職場も独身だらけよ。
だれの責任でもないし、別に批判されることでもないが、こんな話がぼくのまわりだけでもゴロゴロある。
わが家はさいわい二人の息子に恵まれた。だが、ぼくの家系の存続もだんだんあやしくなってきた。
このままでは、そのうち結婚する相手がいればどんな人だっていい、なんてことになりかねない。ある日突然、銀歯がギラリと光る中年のオバサンが息子の嫁さんになっても、決してがっかりしたり、目をそらしてはいけないということか。
一発、逆転を祈るのみ。
■写真は、4月9日のブログで紹介したレンゲ畑の隣から撮影したもの。今年も菖蒲の花がきれいに咲いている。
厚生労働省の発表によると、全国の自治体が2020年の1年間に受理した妊娠届の件数は前年比4・8%減の87万2227件で、過去最少を更新した。そのため21年の出生数は80万人を割り込み、70万人台になることが濃厚という。
減少の原因はまたしてもコロナウィルスにあるらしい。感染拡大による出産や子育ての不安から「妊娠控え」が起きたようだ、というのである。
理由はともあれ、とうとう1年間に生まれる子どもの数が80万人を切るという。実に恐るべき事態と言わざるをえない。
試みに、80万人のあかちゃんが大人になったとき、子どもの数がどうなるか、簡単な計算をしてみよう。
80万人のうち、男と女の割合が半々と仮定すると、女性の数は40万人。その全員が子どもを2人ずつ産むと80万人。これなら現状を維持できる。
しかし、それはまったく非現実的な話である。
いまでも30代後半の女性で未婚の人は全体の約3割もいる。この状況が将来も続くとしたら、女性40万人のうち、30代後半までに結婚する女性は、日本中でたった28万人しかいないことになる。これは福岡ソフトバンクホークスのホームゲームが満席で、わずか7試合やれば(合計観客数は26万9920人)、ほぼ到達する人数でしかない。
もちろん、結婚せずに子どもを育てるシングルマザーの人たちもいるだろうが、大勢には影響ないだろう。これでどうやって、わが国の人口を増やすというのだろうか。
もうひとつ、ぼくは人口減について、別の計算をしたことがある。
国の推計では、2065年の日本の人口は3,900万人も少なくなる。これは現在の大阪府より以西の中国、四国、九州・沖縄の全府県を合計した人口と同じ数である。つまり、来年生まれる子どもたちが43歳になったときには、いま大阪から西に住んでいる人口分がすっぽり消えてなくなっているのだ。あくまでも推計ではあるが。
もはや、想像を絶する日本の姿である。だが、このままではそうなってしまう。
このあたりのことを政府の発表はともかく、新聞やテレビは「少子高齢化社会」というお決まりの言葉ではなく、もっと身近に、わかりやすく、リアルに報道できないものかとおもう。
身につまされる話はぼくのまわりにもいっぱいある。自分の代で、家系が絶えてしまうという人がたくさんいるのだ。
子どもがいない。息子はいるけど、結婚する気もないし、相手もいない。養子になってくれる人なんていない。まだまだと言っている間に、適齢期を過ぎてしまった。本人も親も焦っているけど、まったくご縁がない。うちの職場も独身だらけよ。
だれの責任でもないし、別に批判されることでもないが、こんな話がぼくのまわりだけでもゴロゴロある。
わが家はさいわい二人の息子に恵まれた。だが、ぼくの家系の存続もだんだんあやしくなってきた。
このままでは、そのうち結婚する相手がいればどんな人だっていい、なんてことになりかねない。ある日突然、銀歯がギラリと光る中年のオバサンが息子の嫁さんになっても、決してがっかりしたり、目をそらしてはいけないということか。
一発、逆転を祈るのみ。
■写真は、4月9日のブログで紹介したレンゲ畑の隣から撮影したもの。今年も菖蒲の花がきれいに咲いている。
こっちの身にもなってみろ ― 2021年05月31日 18時39分

右奥下の親シラズがズギズキして、冷たい水が当たるとジーンとしみる。顔をしかめるほど痛い。2週間ほど我慢していたが、ようやく診察予約の日がきたので歯医者に行ってきた。
ゆっくり歩いて10分ほど。そこに行き着くまでに同業者が3軒もある。このあたりは歯科医だらけだ。産婦人科や小児科はまったくない。
ぼくが行く歯医者の近くにある広さ5反ほど畑は、例年ならまもなく水が引かれて田植えが始まるころだが、先日、建設計画の看板が立てられた。またもや有料老人ホームができるという。3階建てだから、このあたりの風景は一変するだろう。
自宅から歩いて4、5分のところにあった、サッカーコートが何面もとれぐらいに広かった畑も老人施設に化けた。新しくできる建物は年寄り相手のものが多い。葬儀社の建物もずいぶん増えた。一方で息子たちが通っていた小学校は空き教室だらけになっている。まるで、いまの日本の縮図を見るようだ。
若い人にはピンとこないだろうが、ぼくのなかでは歯医者と老人施設はひとつの線上にある。だって、今日も歯医者から、こう言われたのだ。
「うーん、この親シラズは抜歯するしかないですね。仕方がないですよ、もう年だから。いまの若い人は、親シラズは抜くんですよ。まぁ、よく長持ちしたということですね。××さんは平均寿命まであと15年ぐらいですか。生きている間は入れ歯にならないようにしないとね。ま、もう少し、様子を見てみましょうか。できるだけ抜かないですむように、頑張りましょう」
最後は「頑張りましょう」と励ましてくれたが、ぼくの経験則では、それは気やすめに過ぎず、本当のところは「覚悟してね」という意味である。
すでにこの歯医者の手によって、ぼくの歯は4本も抜かれた。原因はすべて歯周病だから、ここまでほうっていた自分が悪い。たぶん、早ければ次回の診察日にも、医者はこう言うだろう。
「あー、こりゃあ、もう駄目だわ。ほら、こんなにぐらぐらしている。抜きましょ、それしかないですよ。××さぁん、抜歯の用意をして」
1本目を抜かれたときも、2本目、3本目、4本目のときも、そう言われたのだ。こちらの未練を断ち切るように、実にあっさりと宣告して、たちどころに行動に移すのだ、この人は。
ぼくよりも若い50代前半だが、腕のよさが評判で、施術も説明も的確だし、話す内容にも説得力があるので、この人から言われたら覚悟を決めるしかない。カミさんも十数年来、この歯医者さんを信頼していて、いわば、ぼくたち夫婦の歯の主治医である。
でも、本人の前でしゃべったことはないが、患者として、言っておきたいことがある。
こちらは言われた通り、いつも素直に従っているけれど、仰向けに寝かされて、口のところだけ開いた布をかぶされて、すっぽり目隠しをされている上に、口は開けたままだから、何を言われても、無抵抗のまま返事の仕様がないのだ。
聞きたいことや言いたいことはいっぱいあるのに、ただ「ふぁい(はい)」とか、「ううえ(いいえ)」としか言えない。しょぼんとして、何もできず、言われっぱなし、やられっぱなしなのがクヤシイ。一度、面と向かって、オイッ、コラッ、おとなしくやられているこっちの身にもなってみろ、と言ってやりたい。
さて、いよいよ書きたくないことを書かねばならぬ。
今日は、痛む親シラズの治療をしてくれなかった。何でも、施術の順番があるとかで、別の歯のところをきれいにして終わりだった。肝心の親シラズには痛み止めを塗られただけ。そして、最後にこう念を押されたのだ。
「これで痛みはやわらぐでしょう。それでも痛くて、我慢できなくなったら、もう、抜くしかないですよ」
かくして、その後のいまの症状は-、
期待したほど痛みはひいていない。冷たい水を口に含むと、鋭い痛みがカチーンと頭に響く。ということは……。
作家の三浦哲郎は随筆の中で、こんなことを書いていた。
彼は郷里の味の身欠き鰊(ニシン)が大好物なのだが、歯がぐらぐらになって、明日、幼馴染みの歯科医から前歯を数本抜かれることになった。そこで、いまのうちに味の見納めをしようと、脂の乗った身欠き鰊を手に入れて、宿泊先のホテルに戻ると、明日はもう無くなってしまう前歯で、身欠き鰊の棒をやんわりと噛んだ、という話だった。
ぼくの前歯は大丈夫である。でも、右下の奥歯は親シラズとブリッジしてあるから、支柱になっている親シラズがなくなると橋(ブリッジ)は崩壊して、奥歯一帯はがらんどうになってしまう。まるで口の中に小学校の空き教室ができるようなものだ。
最後の奥歯で何を食べようかな。まったく年寄りじみた話になってしまったが、いまはそのことが切実なテーマになっている。
ゆっくり歩いて10分ほど。そこに行き着くまでに同業者が3軒もある。このあたりは歯科医だらけだ。産婦人科や小児科はまったくない。
ぼくが行く歯医者の近くにある広さ5反ほど畑は、例年ならまもなく水が引かれて田植えが始まるころだが、先日、建設計画の看板が立てられた。またもや有料老人ホームができるという。3階建てだから、このあたりの風景は一変するだろう。
自宅から歩いて4、5分のところにあった、サッカーコートが何面もとれぐらいに広かった畑も老人施設に化けた。新しくできる建物は年寄り相手のものが多い。葬儀社の建物もずいぶん増えた。一方で息子たちが通っていた小学校は空き教室だらけになっている。まるで、いまの日本の縮図を見るようだ。
若い人にはピンとこないだろうが、ぼくのなかでは歯医者と老人施設はひとつの線上にある。だって、今日も歯医者から、こう言われたのだ。
「うーん、この親シラズは抜歯するしかないですね。仕方がないですよ、もう年だから。いまの若い人は、親シラズは抜くんですよ。まぁ、よく長持ちしたということですね。××さんは平均寿命まであと15年ぐらいですか。生きている間は入れ歯にならないようにしないとね。ま、もう少し、様子を見てみましょうか。できるだけ抜かないですむように、頑張りましょう」
最後は「頑張りましょう」と励ましてくれたが、ぼくの経験則では、それは気やすめに過ぎず、本当のところは「覚悟してね」という意味である。
すでにこの歯医者の手によって、ぼくの歯は4本も抜かれた。原因はすべて歯周病だから、ここまでほうっていた自分が悪い。たぶん、早ければ次回の診察日にも、医者はこう言うだろう。
「あー、こりゃあ、もう駄目だわ。ほら、こんなにぐらぐらしている。抜きましょ、それしかないですよ。××さぁん、抜歯の用意をして」
1本目を抜かれたときも、2本目、3本目、4本目のときも、そう言われたのだ。こちらの未練を断ち切るように、実にあっさりと宣告して、たちどころに行動に移すのだ、この人は。
ぼくよりも若い50代前半だが、腕のよさが評判で、施術も説明も的確だし、話す内容にも説得力があるので、この人から言われたら覚悟を決めるしかない。カミさんも十数年来、この歯医者さんを信頼していて、いわば、ぼくたち夫婦の歯の主治医である。
でも、本人の前でしゃべったことはないが、患者として、言っておきたいことがある。
こちらは言われた通り、いつも素直に従っているけれど、仰向けに寝かされて、口のところだけ開いた布をかぶされて、すっぽり目隠しをされている上に、口は開けたままだから、何を言われても、無抵抗のまま返事の仕様がないのだ。
聞きたいことや言いたいことはいっぱいあるのに、ただ「ふぁい(はい)」とか、「ううえ(いいえ)」としか言えない。しょぼんとして、何もできず、言われっぱなし、やられっぱなしなのがクヤシイ。一度、面と向かって、オイッ、コラッ、おとなしくやられているこっちの身にもなってみろ、と言ってやりたい。
さて、いよいよ書きたくないことを書かねばならぬ。
今日は、痛む親シラズの治療をしてくれなかった。何でも、施術の順番があるとかで、別の歯のところをきれいにして終わりだった。肝心の親シラズには痛み止めを塗られただけ。そして、最後にこう念を押されたのだ。
「これで痛みはやわらぐでしょう。それでも痛くて、我慢できなくなったら、もう、抜くしかないですよ」
かくして、その後のいまの症状は-、
期待したほど痛みはひいていない。冷たい水を口に含むと、鋭い痛みがカチーンと頭に響く。ということは……。
作家の三浦哲郎は随筆の中で、こんなことを書いていた。
彼は郷里の味の身欠き鰊(ニシン)が大好物なのだが、歯がぐらぐらになって、明日、幼馴染みの歯科医から前歯を数本抜かれることになった。そこで、いまのうちに味の見納めをしようと、脂の乗った身欠き鰊を手に入れて、宿泊先のホテルに戻ると、明日はもう無くなってしまう前歯で、身欠き鰊の棒をやんわりと噛んだ、という話だった。
ぼくの前歯は大丈夫である。でも、右下の奥歯は親シラズとブリッジしてあるから、支柱になっている親シラズがなくなると橋(ブリッジ)は崩壊して、奥歯一帯はがらんどうになってしまう。まるで口の中に小学校の空き教室ができるようなものだ。
最後の奥歯で何を食べようかな。まったく年寄りじみた話になってしまったが、いまはそのことが切実なテーマになっている。
最近のコメント